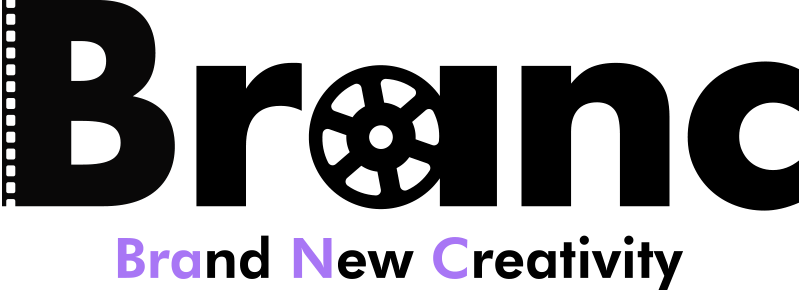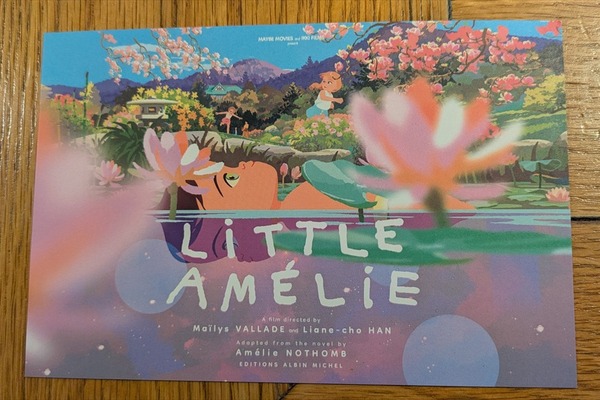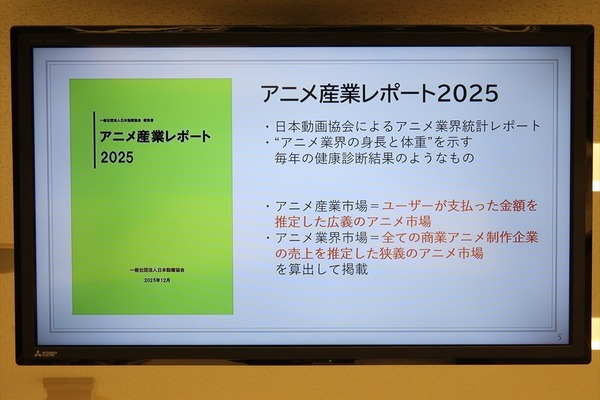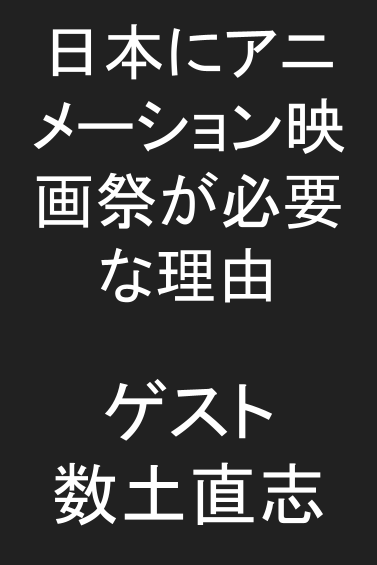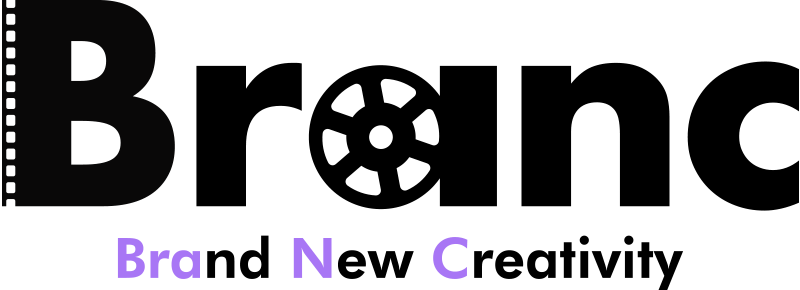第37回東京国際映画祭の一環として、第14回MPAセミナーが行われ、映画監督の中島良氏の「人間とAI、共創の時代へ:アニメーション、実写映像のAI活用事例と未来展望」と題した講演が開催された。
中島良氏は、自身が生成AIを活用して制作した『死が美しいなんて誰が言った』という作品を基に、作品への反響やクリエイターとAIが共存するための考え方を語った。
本作は絵コンテではなく、実際の俳優の動きをモーションキャプチャーで取り入れ、実写撮影と同じような考え方で制作。iPadをVRカメラとして使用し、カメラアングルを決めたり、VRライティングも行ったという。AIは、本来高度な技術が必要で時間もかかる最後の仕上げ部分で使用され、キャラクターの陰影のクオリティアップに活用された。しかし、手書きの修正も最終的には多くなったとのことだ。
フランスと韓国、映画祭での反応の違い
また、同作はフランスのアヌシー国際アニメーション映画祭と韓国の富川ファンタスティック国際映画祭に出品されたが、それぞれの国によって反応が異なったという。
アヌシーでは伝統的な職人の技術を評価する価値観が根付いており、元々AIに批判的な人も多い。AIを使ったMV作品の上映時はブーイングが巻き起こっていたが、本作では拍手が起きたとのことで、中島氏は「キュレーターの方に『AIで作ったというよりは、人間のパフォーマンスによって作られているということが伝わったんだと思う』と言われた」と振り返った。一方で配信権利の販売は苦戦し、AIを導入した作品の風当りの強さを実感したと語った。
一方、富川ではテクノロジーを推進する考えが多く、韓国政府もAIの積極的な活用を奨励しているため、寛容だったよう。クリエイターのためのAIワークショップも行われ、それぞれの国の文化的背景によって考え方はかなり異なることを体感したとのことだ。