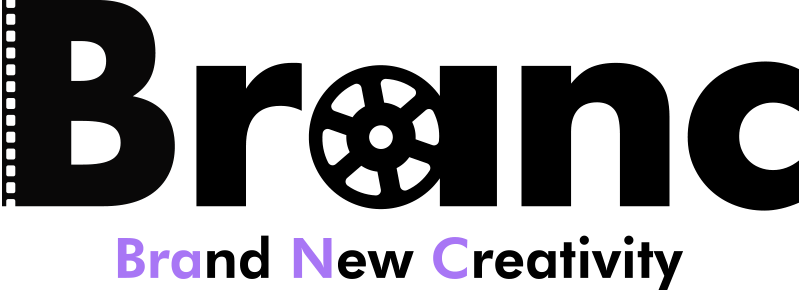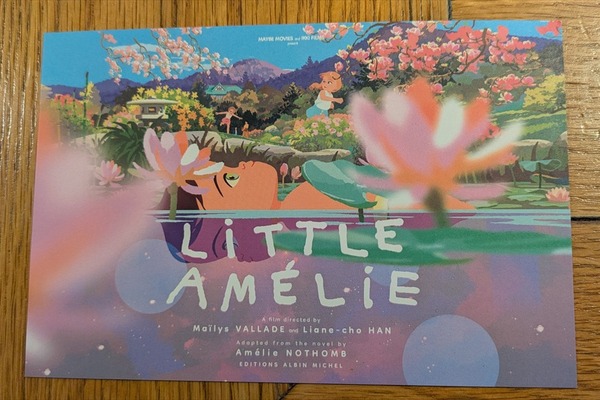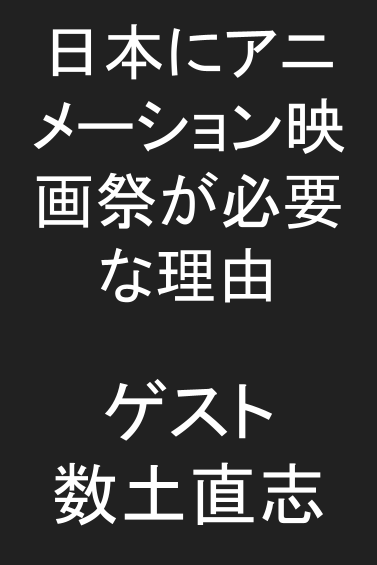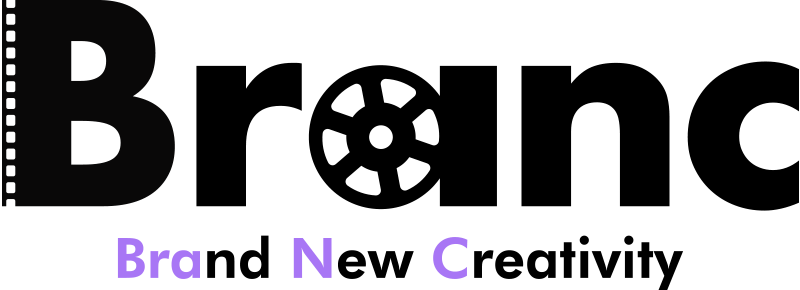10月28日(月)~11月6日(水)の日程で開催される第37回東京国際映画祭で、女性監督の作品や女性の活躍をテーマにした作品を紹介する「ウィメンズ・エンパワーメント部門」を新設することになった。
東京国際映画祭は、アジアの映画祭として初めて、映画界の男女平等を推進している国際団体「Collectif 50/50」に2021年に署名。これまでも映画産業で活躍する女性にスポットを当てる公式プログラム「ウーマン・イン・モーション」などのトークセッションを開催してきたが、これまでよりも一歩進んだ女性活躍を推進するために、新たな部門の新設が実現した。
第一回の開催となる本プログラムのシニア・プログラマーを担当したのは、マケドニア出身で、日本で映画を学び現場も経験したことのあるアンドリヤナ・ツヴェトコビッチ氏だ。自ら映画監督として作品を発表し、映画界での活躍に留まらず、初代マケドニア駐日大使も務めるなど異色の経歴を持つ。「ウィメンズ・エンパワーメント部門」の新設にどのような狙いがあるのか、そしてより多くの女性スタッフが日本の映画産業で活躍するために邦画産業は何をすべきなのか、話を聞いた。
新部門設立の狙いは「アウェアネス」
――新部門「ウィメンズ・エンパワーメント」のシニア・プログラマーに就任した経緯を教えてください。
まずは、私自身の日本映画との関わり、東京国際映画祭との関係についてからお話しします。私は日本映画に憧れて、日本大学芸術学部で映画を学び、博士号を取得しました。日本在住歴は22年になります。日本映画監督協会のメンバーでもあり、松竹の時代劇の脚本を担当したり、助監督も経験するなど、映画業界に関わってきました。その後、色々あって、マケドニア駐日大使にも就任しました。

日本の映画業界を経験して感じたことは、他国に比べて女性の映像作家が活躍しにくい状況があるということです。例えば、資金調達に関しても、女性作家をサポートするシステムが弱いと感じています。そのため、パンデミックの中で東京国際映画祭と関わることになり、若い作家のための様々な施策をサポートすることになりました。
例えば、Amazon Prime Video テイクワン賞を2020年に提案し、翌年に実現、審査委員も務めました。昨年には、ジェンダー平等と地球環境をテーマにした「SDGs in Motion」という企画でチーフキュレーターもやっています。そうした経験を積み重ね、今回、市山プログラミング・ディレクターと安藤チェアマンに、女性監督へスポットを当てる新部門の創設にあたり、お声がけをいただきました。 大変光栄であると同時に、ここから新しい映画祭の歴史を生み出していきたいという気持ちでいます。
――この新部門は、日本の映画産業全体に対して、どんな意義があるとお考えですか。
この新部門の狙いは「アウェアネス」、認知度を高めるということです。女性たちの活躍と進出に対して、日本の映画産業が問題を抱えているということを、大手映画会社から小さな制作会社にいたるまで、あまねく認識すべきです。これは社会問題であり、人権問題でもあります。そういうメッセージをこの部門を通して発信したいと思っています。
映画が社会の鏡であるとするなら、やはり、世界の様々なストーリーが語られるべきであり、もっと多くの女性の物語を届けねばなりません。こうした活動は、これまで先人たちもやってこられたことです。例えば、日本の女性監督第1号である坂根田鶴子さんや、女優出身の田中絹代さん、東京国際女性映画祭を設立した高野悦子さんなどが、女性たちの活躍を後押しするために戦ってこられました。今回の新部門設立は、改めてそのためのスタートを切ったものと言えると思います。
しかし、これだけでは充分ではありません。私たちは、社会全体でこの問題に対して戦略的に対峙していく必要があります。映画人だけでなく、ジャーナリストの方々も含めて、一丸となって問題解決にあたる必要があると思っています。
ラインナップには現代女性作家の多様な視点が集まる

――「ウィメンズ・エンパワーメント部門」のラインナップについてお聞かせください。様々な国の作品を選ばれていますが、どのようなことを意識して選んだのですか。