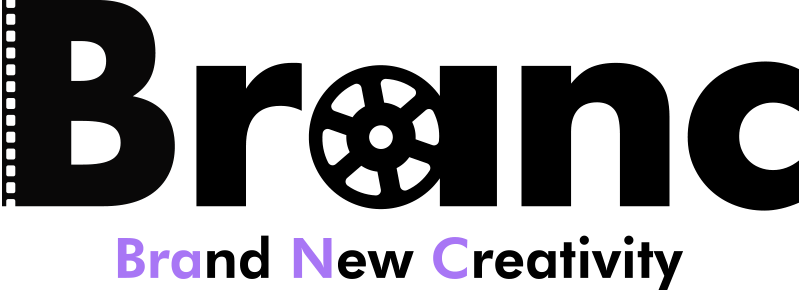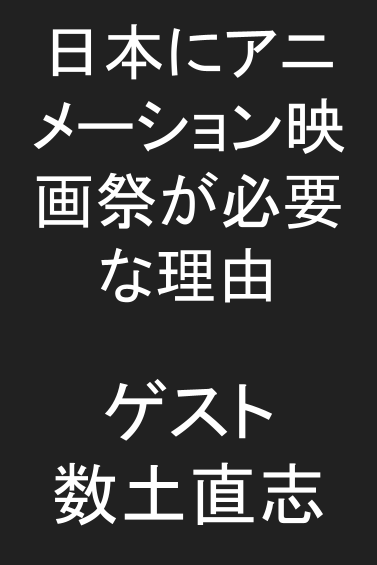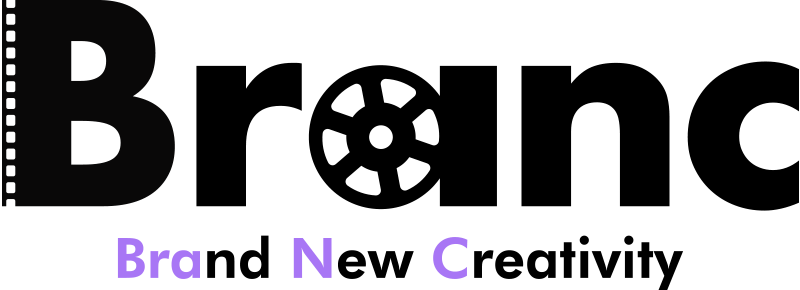台湾の文化コンテンツ産業を支援している行政機関、台湾クリエイティブ・コンテンツ・エイジェンシー (TAICCA/タイカ)主催の大型展覧会「TCCF クリエイティブコンテンツフェスタ(Taiwan Creative Content Fest)」が11月4日から11月7日の日程で開催された(台北・南港展覧館)。
TCCFは、「ピッチング」「マーケット」「フォーラム」の三本柱で構成されている。「ピッチング」では、日本と関係のある企画が多く見られ、日台合作プロジェクトが今後益々増えていく可能性を感じた。また、開催期間中、K2ピクチャーズがTAICCAと覚書(MOU)を調印、日台の共同制作体制を強化して国際的な競争力を持つ映像作品の開発を目指すと発表。MOD、Hami Videなどの配信プラットフォームを傘下に持つ台湾通信大手・中華電信も新作発表会を開き、日本のサブ監督が手がけるドラマ「阿茲海默警探」(アルツハイマー刑事)の製作を明らかにした。
しかしブログラム全体を見渡すと、目を引いたのは韓国や東南アジアの国々とのコラボレーションに関する企画だ。台湾の文化コンテンツのグローバル展開を目指す台湾にとって、韓国はビジネスモデルのよき模範として、東南アジアには市場として期待を寄せていることがうかがえた。

では、台湾が日本とのコラボレーションに期待していることは何か?2024年には『青春18×2 君へと続く道』がヒット、今年秋に日本で公開された『Dear Stranger/ディア・ストレンジャー(以下ディア・ストレンジャー)』は今年の台湾金馬映画祭のクロージング作品に選ばれるなど、日台のコラボレーションが新しいフェーズに入ったことを感じる近年。台湾とは今後、どのような形で協力していけるのか? TCCF の会場で、『ディア・ストレンジャー』台湾側の共同プロデューサーである徐國倫(シュー・グオルン)氏とポストプロダクション・プロデューサーの林香伶(リン・シアンリン)氏にお話を聞いた。
『ディア・ストレンジャー』に台湾が参加することになった理由
――『ディア・ストレンジャー』で台湾側が関わったのは、具体的に製作過程のどの部分でしょうか? また、日台合作となった経緯を教えてください。
林香伶氏(以下、林):全編米国で撮影された作品なので、台湾側が関わったのは、編集やカラーグレーディング、サウンドミキシングからDCP(デジタルシネマパッケージ)の作成まで、主にポストプロダクションの部分です。
合作の始まりは2019年でした。徐さんと私が製作した『江湖無難事(原題)』(2019)という作品の撮影で日本に行った時、本作の朱永菁プロデューサーにご協力いただくご縁がありました。それで今回、台湾の俳優を起用し、国際共同製作でこの作品を作りたいということで、朱さんから徐さんにお話があったというのがきっかけです。
徐國倫氏(以下、徐):林さんの話を補足すると、私と朱さんの出会いは『私を月に連れてって』(2018、第13回大阪アジアン映画祭で上映)にさかのぼります。その後、林さんと一緒に製作した『江湖無難事』でも朱さんに協力してもらいました。私が日本とよく仕事をしている理由は、実はそれよりもっと前、魏徳聖(ウェイ・ダーション)監督の『KANO 1931海の向こうの甲子園』(2014)を撮った時に多くの日本の俳優やスタッフと仕事したことがきっかけなのです。ですから、日本側の仕事の仕方にはかなり慣れていると思います。
以前から日本でお世話になったお返しをしたいという思いがあったのですが、なかなか実現できずにいました。今回、朱さんから『ディア・ストレンジャー』のお話をいただいた時には既にTAICCAが設立され、積極的に日本とのプロジェクトを支援しようとしている時期だったので、そのタイミングでTAICCAの「国際合作投資計画2.0(TICP 2.0)」を申請しました。台湾と日本、それぞれが自国の規定に合わせて補助金などを申請し、その後、双方の規定などを確認しながらすり合わせていったという流れですね。複雑でしたが我々にとっても新しい経験ができました。

――台湾側の出資比率はどのくらいなのですか?
徐:40パーセント近くに上ります。「TICP 2.0」を通したTAICCAからの投資だけではなく、他の台湾企業数社からも出資を受けています。
――日本は映画を作る時、製作委員会方式で出資することが多いですが、台湾とは異なりますよね? 日本と合作する上で、やりにくいと感じる部分はありますか?
徐:たしかに日本の製作委員会方式は、他に類のないやり方ですよね。でも『ディア・ストレンジャー』については撮影場所が米国だったため、撮影経費は米国のやり方で決算し、台湾で使った分は台湾、日本の分は日本のやり方で進めるという方法で採用しました。
――台湾と合作したことで、作品のクオリティにどんな影響があったと思いますか?
林:ご存じのように真利子哲也監督は作家性の強い映画監督です。たとえば壊れた車の音など、ここは必ずこうして欲しいというこだわりがある。ポスプロに参加した台湾側のパートナーは協力的で仕事ぶりも細やかなので、監督が求める効果を1つ1つ実現していくことができたと思います。これが台湾側が提供できるサービスのいいところだと思います。
言語の壁は課題と同時に強みでもある
――日本との合作で、今後の課題だと思った部分、また将来性を感じた部分があれば、それぞれ教えてください。
林:難しいと思ったのは、言葉の問題ですね。今回は母語が中国語以外のスタッフが何名もいました。たとえば、編集のマシュー・ラクロー(『鵞鳥湖の夜』『新世紀ロマンティクス』など)は台湾を拠点に活動していて中国語も話せますが、仕事の時は英語の通訳が必要で、3か国語でやり取りをすることもありました。日本語は台湾華語や英語と比べ、細かいニュアンスを含んだ言葉です。たとえば日本語が伝える感覚的なものや雰囲気的なものに関して、台湾人やその他の国のスタッフは空気を読みきれないことが多く、すり合わせに少し時間がかかります。日本のスタッフとは親しい関係を築けているので、長くはかからないのですが、ポストプロダクションの全ての工程で、チームが変わるたびに同じプロセスを経ることになります。ただ、これも日本に限らず、どこの国との合作でも同じです。近年では韓国と仕事をする時も同様の経験を積み重ねていますし、通訳のレベルはどんどん上がっていると思います。AIで代用できると言う人も多いですが、日本語はAIには難しい(笑)。通訳人材の育成という部分でも、安定的に手配できるようになってきたと思います。
徐:大事な会議の時は、日本語と中国語のどちらも話せる朱さんが通訳してくれました。説明が難しいシチュエーションでも、彼は中国語も監督が言いたいこともよく分かっているので、話し合いに加わってくれました。
――日本語はハイコンテクストな言語だとよく言われますからね・・・。
徐:日本人は「これはぜひお願いします」というような言い方をされる場合がありますよね。控えめな言い方ですが、日本語をよく分かっている人から「絶対やってほしいということです。相談の余地はありません」と教えられました。
でも実は、日本側も同じことを考えていると思いますよ。台湾人も婉曲的な言い方をすることが多いのです。たとえば欧米人なら「ノー」「無理」と言うシチュエーションでも、「ちょっと難しいですが、やってみましょう」という言い方をする。でも長く付き合っていくうちに、言葉の問題は減ってくると思います。
でも、実は言語が台日合作のメリットでもあると思います。台湾と日本は、他の国に比べ、相対的に見て互いの文化をよく理解し合っている。それが仕事をする時も、共同制作する作品のストーリーを考える時も、親近感を持って取り組める一因だと思います。韓国、タイ、マレーシア、ベトナムを相手に同様の関係が築けるかどうかは分かりませんが、日本となら可能です。

台湾にとって、日本と共同製作するメリットとは
――日本と合作することのメリットをどう感じていますか?
林:親近感という面では、たとえば『ディア・ストレンジャー』の場合、台湾人は皆、西島秀俊さんをよく知っていますし、ハリウッド映画などと違ってプロモーションでも交流しやすいですね。
スタッフの面で言えば、技術的な交流ができることも合作の面白さだと思います。たとえば、私たちが担当したポストプロダクションの部分では、本作のカラリストのヨブ・ムーア(近年の作品は『ロストランド』『Nouvelle Vague』など』)はカンヌ国際映画祭で受賞した作品に数多く関わっている人です。それから台湾在住のマシュー、サウンドミキシングの杜篤之さんは皆さんもご存じの大ベテランです。お互いどんな技術を使っているのか研究しながら協力し、技術面でもクリエイティブな面でも、いい意味でぶつかり合いながら仕事ができるのは合作の素晴らしさだと思います。
徐:ダイレクトな言い方になりますが、台湾は人口も映画館数も少ないので、市場の開拓が必須です。これまでも台湾映画は日本で公開されてきましたが、どれも公開規模が小さかった。合作にすることで、将来的に、日本でも中~大規模な公開が見込める作品を台湾も一緒に作っていけることを願っています。
――日台で合作が成立しやすいのは、どんなジャンルの作品だと思いますか?
林:特定のジャンルというより、“どう合作するか”を見るべきですよね。今回はニューヨークが舞台の物語だったので、台湾は技術面とポストプロダクションからの参加になりましたが、物語によってさまざまな可能性があると思います。
徐:台湾と日本、両方の観客に受け入れられる最大公約数的なところを考えると、“分かりやすいジャンル”という答えになりますが、“分かりやすい”と言っても、ラブストーリーにも複雑なものやシンプルなものがありますし、アクションにしたってそうですよね。これはどちらから合作を提案する場合も同じですが、観客の鑑賞の妨げになる要素はないか、どんな調整が必要になるかは考えます。たとえば、さっき話した言葉の問題。双方の俳優が出演するなら、どちらの言語を使って、どうやり取りさせるかが重要です。
――たしかに、NHKで放送されたドラマ「火星の女王」には台湾の俳優、林廷憶(スリ・リン)さんが出演されましたが、彼女の役は火星育ちという設定で日本語が苦手だという言葉の障壁をクリアしていましたね。プロデューサーとして、日本側からの企画にどんな要素があれば、台湾との合作が実現しやすいと考えますか?
徐:“必勝の公式”はありませんが、キャラクターが魅力的がどうか、物語が感動的かどうか、やはりストーリーそのものを見て考えますね。相手の製作チームを見て判断することも。個人的な感想ですが、日本の作り手には、新しいスタイルを試そうとしている人が多いのかなと感じます。相手が新しいことにトライしようとしているなら、こちらもそれを受け止めたい。たとえばネットフリックスを見ると、日本のドラマシリーズが明らかに増えましたよね。ネットフリックスだとテレビではできなかった大胆な表現が可能です。これが配信サービスの普及がもたらした変化だと思います。
「TCCF クリエイティブコンテンツフェスタ(Taiwan Creative Content Fest)」