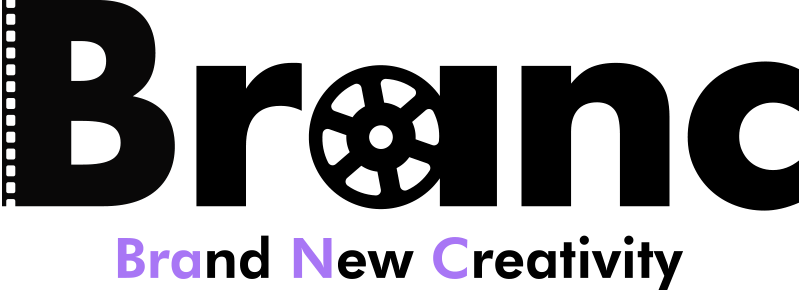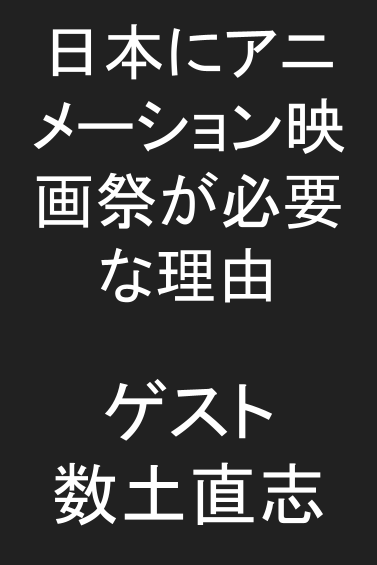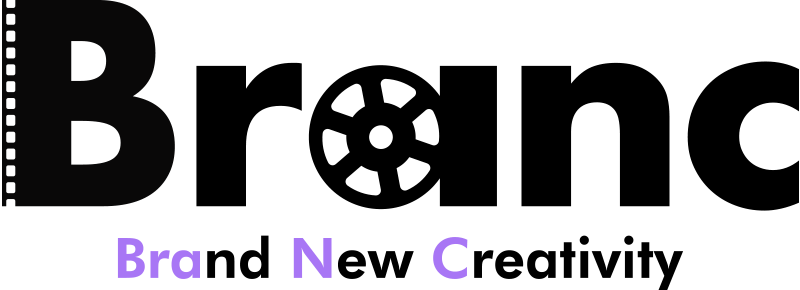11月29日から公開が始まった映画『みんな、おしゃべり!』は、ろう者とクルド人コミュニティの対立から生じる騒動を、ユーモラスに描いた作品だ。
ろう者が営む電器店の近くにクルド人が店を構えることになった。ある日、ささいなすれ違いから対立が発生。しかし、クルド人たちは日本語を話せず、ろう者もクルド語はわからない。そんな2つのコミュニティの板挟みとなるのは、古賀家で唯一の聴者でCODA(Children of Deaf Adults)である夏海とクルド人一家で日本語を話せるヒワの2人。ことあるごとに誤解が大きくなっていくなか、夏海の弟の駿がとある“言語”を生み出し、それが波紋を広げていく。
現代社会は多様性が大事だと言われる中、その多様な人々が集まることでぶつかり合いが起きる様をユーモア混じりに描くのは、自らもCODAとしての出自を持つ河合健監督。
本作の狙いについて、河合監督に話を聞いた。

「絶対に寄り添わない」――あえて“わからなさ”を生む演出
本作の構想は、河合監督の出自とも関わっている。親がろう者でCODAである河合監督は、いつかろう者が登場する映画を撮りたいとは思っていたものの、自身のアイデンティティへの迷いからそのテーマを遠ざけていたという。しかし、言語を軸に物語を構築することで自分の抱えていた課題が見えてくるのではと考え、CODAに近い葛藤を抱える存在として、外国から移住してきた家族の、日本生まれの子どもの存在に着目したことで本作の構想が動き出した。
「言語」がテーマなだけあって、本作は、日本語、クルド語、日本手話など複数の言語が飛び交う。そのため、字幕は必須となるわけだが、河合監督は字幕を単なるアクセシビリティのためではなく、演出的な意図をもって使用している。
例えば冒頭、クルドの会話シーンがあるが、ここでは日本語字幕ではなくクルド語の字幕が表示される。ここは日本語を第一言語とする人には理解できない言葉をしゃべっていることを伝えるシーンであり、ろう者にもそのことを伝えるために、敢えてクルド語を字幕で出している。
河合監督はこのシーンについて、「バリアフリーのための字幕では『外国語の会話』みたいに表示されることがありますが、それは情報だけで面白さがない。何語でしゃべっているのかわからないということを、ろう者にも能動的に体験してほしいので、敢えてクルド語を表示しています」と語る。
また、後半は字幕が少なくなっていく。河合監督はその点について「わからないことを含めて楽しんでほしい」と語る。
「今の世の中は、なんでもわかろうとする傾向がありますけど、結局、他人のことってわからないものだと思うんです。この作品は絶対に全部を理解させないぞというつもりで作っています」

河合監督は、そうしたお互いの言語がわからない者同士が映画館に集まることで、自宅で配信作品を見るのとは異なる面白さが作れると考えたという。そのため本作の制作にあたっては、映画館の客席をどうデザインするかに意識を向けたそうだ。
「隣には自分とは違う第一言語の人がいて、言語が違うからこそ笑うタイミングが違っていたり、わからない部分もある。そのずれ自体が、配信やテレビを個人で視聴するのとは異なる鑑賞体験になると思ったんです。だから、ろう者にしかわからない描写もあるし、クルド語にがわかる人にだけわかる描写も入れています」
聴者優位の社会では、聴者が気がつかない視点が多々ある。そうしたことを聴者にわかるように説明的に描いてしまうと、結局それは「聴者のための映画」となる。河合監督は単なる「マイノリティ紹介映画じゃなくて、ろう者が見て面白いものを作りたかった」と強調する。
そのため、企画段階から河合監督は「寄り添わない」ことを意識して映画を作ったという。視覚言語と音声言語には明らかに違いがあり、CODAである河合監督ですらどんな弊害があるのか、完全にはわからないものだと語る。その違いから目をそらして「わかったつもりになっても仕方ない。聴者に対して説明的な映画を作って、知ったつもりになれるような映画は作りたくなかったんです」と河合監督は言う。

文字起こしアプリの精度の高さに驚き、劇中でそのまま使用
作中で描かれる言語間のディスコミュニケーションを通じ、河合監督は言葉を「ツール」と「アイデンティティ」の二つの側面から捉えている。本作では特にアイデンティティの側面が強調されており、複雑な歴史的背景を持つクルドの人々や手話を第一言語とする人々を、安易にカテゴライズすることなく、その複雑さを維持したまま描こうと試みたという。
一方で、ツールとしての言葉を象徴するのが、劇中に登場する文字起こしアプリ「YY文字起こし」だろう。ろう者の知人からの推薦で導入されたこのシステムの精度の高さに、河合監督は驚いたという。

通常、映画撮影で画面に文字を表示させる際は、作り込んだ素材を用意することが多い。しかし、本アプリは精度が高いため、現場でリアルタイムに使用することが可能となった。これにより、役者のアドリブや、語尾の細かなニュアンスにも即座に対応でき、演出の自由度を大きく広げる結果となった。作り込みでは不可能な、現場のライブ感をそのまま映像に収めることができたという。
【関連記事】
ろう者のマーケットを可視化できるか
映画産業において、言語の違いはマーケットサイズの違いでもある。英語と日本語では明らかに市場の大きさが違うように日本手話の市場サイズも異なる。これまで「ろう者」という存在を、映画産業は確かな市場として認識してこなかっただろう。字幕表示のためのアプリの普及や機器の貸出などを行う劇場も増加してはいるが、まだまだ対応している作品が多くない。とりわけ、予算の厳しいインデペンデント映画では顕著だ。

河合監督はこの現状に対し、ろう者を明確なターゲット、すなわちマーケットとして捉える挑戦を本作で行っている。ろう者に対して「明確にあなたたちをお客さんとして想定した作品を作りましたと言えるものにしたかった」と語る。
「その試みがどこまで成功するかわかりませんが、映画館の運営側に『ろう者も劇場にたくさん来るんだ』と思ってほしい。そうなれば、ろう者の監督作品や、ろう者を題材にした企画の上映も増えて、表現の幅も広がるはずです」
中途失聴者や、高齢化に伴う難聴者を含めれば、その潜在的な市場規模は決して小さくないはず。本作は、映画界における新たなマーケットの可能性を切り拓く試金石とも言えるだろう。