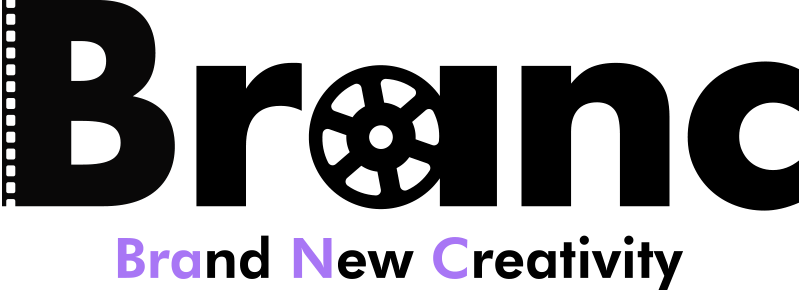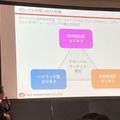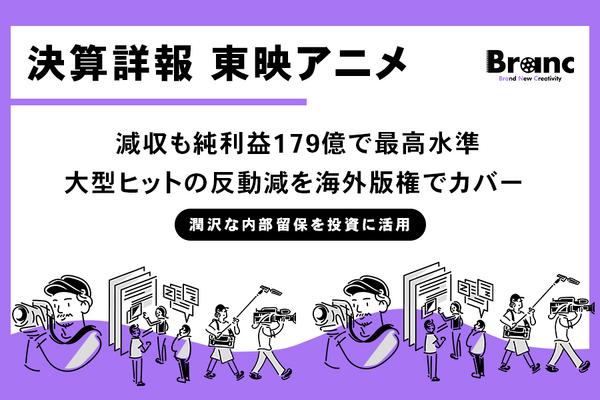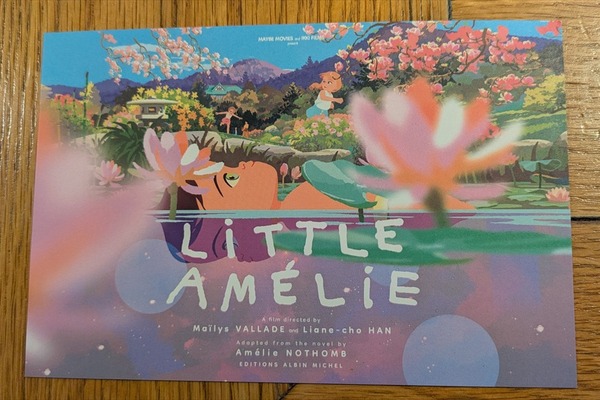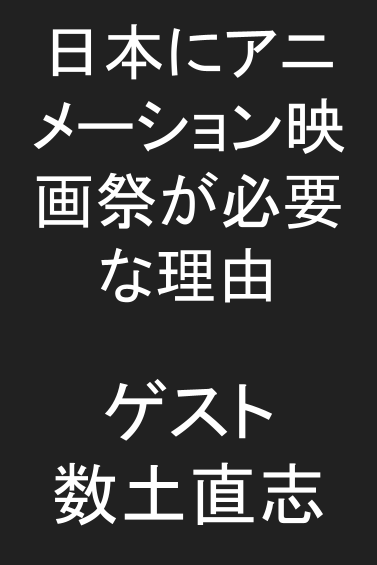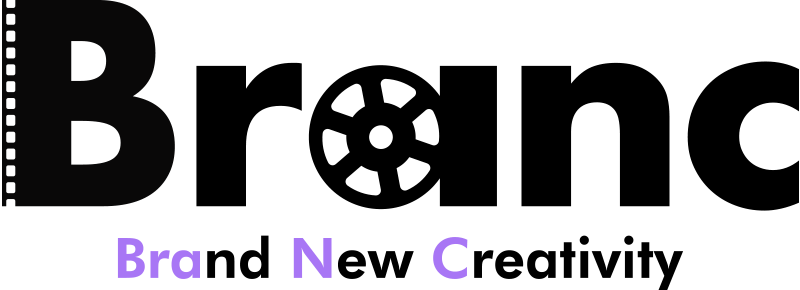Photo by Eugene Gologursky/Getty Images for ReedPop
東京国際映画祭と並行して開催されるアジア最大級の映像コンテンツマーケット「TIFFCOM 2023」にて、「東映アニメーションの海外戦略について」と題したセミナーが開催された。
近年、東映アニメーションは「ONE PIECE」や「ドラゴンボール」、「SLAM DUNK」などをグローバル市場で成功させている。そんな同社の海外戦略の歴史と現況について語られた。
このセミナーから見えてくるのは、東映アニメーションはすでにグローバル市場を前提として事業展開しているということ、そして現在の成功は一朝一夕に生まれたものではなく、長い時間をかけて開拓した成果であるということだ。