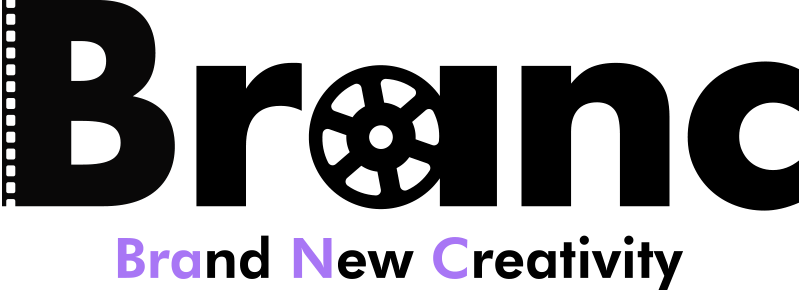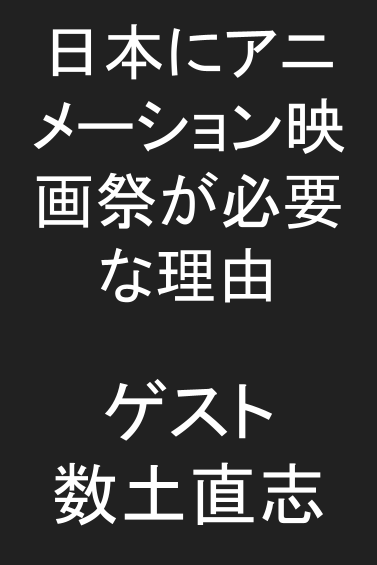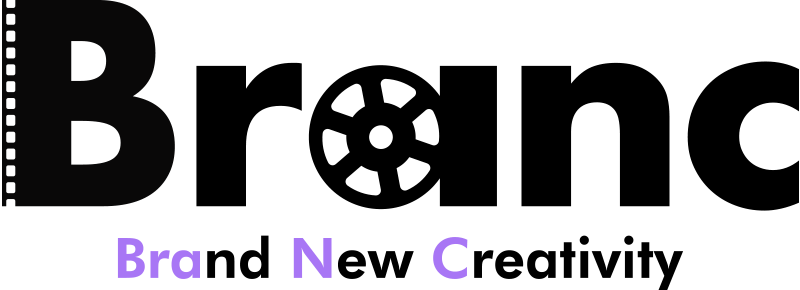2025年12月に開催された、「あいち・なごやインターナショナル・アニメーション・フィルム・フェスティバル」の一環として、アニメ業界における多様性と公平性の向上を目指すシンポジウム「WIAとアニメーション業界の多様性」が行われた。
世界的な団体であるWIA(Women in Animation)代表のマージ・ディーン氏、『どーもくん』や『リラックマ』などを手掛けてきたドワーフ共同創設者の松本紀子氏、そしてソニーグループで多角的なキャリアを歩んできた戸村朝子氏が登壇。横浜国立大学の須川亜紀子教授をモデレーターに、国内外のアニメーション業界が抱える課題と、次世代に向けた展望が語られた。
日本アニメ業界のジェンダーギャップの現状
シンポジウムの冒頭、須川氏は日本アニメ業界における統計データを提示。日本アニメーター・演出協会(JAniCA)の2023年調査によると、回答者の男女比は男性53.9%、女性44%と一見均衡しているように見える。しかし年齢別分布を見ると、女性は38歳を境に急減しており、50代・60代の女性スタッフが極めて少ないという実態を浮き彫りにした。
職種別では、さらに顕著な偏りが見られ、監督・演出は女性が7%、脚本・絵コンテは回答者の100%が男性である一方、仕上げ・彩色は女性が100%を占めたという。

また、JFP(Japan Film Project Research)の調査によれば、興行収入10億円超のアニメ映画において、プロデューサー、監督、制作委員会メンバーといった「意思決定権」を持つ職位の多くを男性が占めている。一方で、アニメーターやアソシエイト・スタッフなど、実作業を担う層には女性が多い。この「意思決定の場における女性の少なさ」が、日本アニメ業界の大きな課題として提示された。
登壇者の実体験:日米の現場から見えた「見えない壁」
続くディスカッションでは、日米の第一線で活躍してきた3名が、自身のキャリアと業界の変遷を振り返った。
マージ・ディーン氏は、日本アニメ業界の統計を見て、米国の状況もかつては同様であり、ディズニーなどのスタジオでも、セル画の着彩部門は「インク&ペイント・ガールズ」と呼ばれ、女性の仕事として固定化されていたと指摘。「創造的な決定がなされた後の、根気のいる作業に女性が割り当てられる傾向」は、日米共通の課題であると述べた。
戸村氏はソニー・ピクチャーズでのキャリア初期、米国流のマネジメント下では女性役員も多く、日本のオフィスでも女性がトップを務める時代だったと回想した。そのため、性別を意識せずに新規事業に邁進できたという。
一方で、キャリアが進みテクノロジー分野に関わるようになると、周囲の男性比率が高まり、特有のコミュニケーション環境を実感したと語った。

戸村氏は「『女性だから』という先入観をなくすことが、より良いポジションに適切な人材を配置する鍵になる」と強調。また、大きな投資を決断する際に女性が自信を持てないケースがあるのではないかと指摘。「自分が鈍感だったから良かったのかもしれない」と自身のキャリアを振り返りつつ、「大きなチャンスが来た時に、責任をとりたくないからと譲っていてはいけない。男女ともに『女性だからできない』と決めつけず、責任ある仕事を任せてみてほしい」と訴えた。
松本氏は、小規模スタジオの経営者として「生きるのに精一杯で性別を意識する余裕がなかった」と語る。しかし、大きな組織や制作委員会と対峙する中で、無意識のうちに存在する「ガラスの天井」を感じる瞬間があったと明かした。
松本氏は、メインストリーム(CGやテレビアニメ)に対する「カウンター」としてのストップモーションという立場が、結果として独自の視点を持つことにつながったと述懐。その上で、単に社会に進出することを目標にするのではなく、自分が何を作りたいのかという目標をしっかりと定めることの大切さを説いた。
次世代に向けて:多様性が生む「組織の強さ」
多様な働き方を実現するための具体的なアクションについても議論が及んだ。マージ氏は、女性が職場で前進する際の最大の障壁の一つとして、「自分を二の次にしてしまう、care-giver(介護・育児の担い手)としての役割意識」を挙げた。自身のシングルマザーとしての経験を引き合いに出し、「キャリアを子供と同じくらい重要だと決断する瞬間が必要だった」という。
松本氏は自社の取り組みを紹介。ドワーフでは、女性スタッフが育児と仕事を両立できるよう、フェアな評価基準のもとで時短勤務を導入している。さらに、同スタジオでは男性の育休取得も進んでおり、「子育ての過酷さを知ることで、上司として部下に優しくなれる」という循環が生まれていることを明かした。

戸村氏は、育休から復帰した男性ディレクターの事例を挙げ、育児の経験がクリエイティブに良い影響を与えたケースも紹介。エンターテインメントは時代の価値観を反映するものであり、経験豊かな人材が揃うことでより良い作品が生まれるという、ポジティブな影響があることを指摘した。
また、女性活躍はそれ自体が目標ではなく、組織がより良質な作品を生み出すための手段であるべきだと語り、若い世代も含めて男女の区別なく働ける環境の方が、名作が生まれやすいと語る。
マージ・ディーン氏は、自身の娘の世代がジェンダーに対して非常にオープンで、多様性を当たり前のものとして受け入れている現状を語った。
松本氏もこれに同意し、現在の20代・30代は実力主義で非常にフラットな感覚を持っていると述べた。一方で、従来の「ジェンダー」という分かりやすい区別や役割が消失したオールフラットな時代においては、クリエイター一人ひとりが自らの軸をしっかり持つ「胆力」が必要になると予測した。

質疑応答:業界構造の変革と「個」の力
会場からは、アーカイブ業務に携わる女性や、国際共同製作に関心を持つ参加者から鋭い質問が寄せられた。
女性監督は確実に増えている一方で、統計上の比率の変化が緩慢である要因について、質問者から「日本のアニメ業界がフリーランス中心の構造であることが、組織的な変化を遅らせているのではないか」との問いが発せられた。
これに対し戸村氏は、文化庁アドバイザーとしてインディペンデントなクリエイターを支援してきた経験から、「日本はフリーランス同士の横の繋がりが弱く、ギルドのような仕組みが欠けている」と分析。コンテンツ産業が国の重要政策と位置付けられる中で、個人のクリエイターが活動しやすい環境を整えるには、行政と産業界が一体となった取り組みが不可欠だと説いた。

一方、マージ氏は米国ロサンゼルスの状況について、テレビアニメは制作の多くを外部委託する構造であり、現場の約4分の1がフリーランス、4分の3がスタジオ所属だろうと推計。所属スタッフが副業としてフリーランス活動を行うことも一般的であり、日本とは異なる雇用形態の流動性があることを示唆した。
松本氏は、自身が身を置くストップモーション業界の特殊な環境について言及。この分野は極めて人手が少なく、必然的に実力のある人材の取り合いになる。常に人手不足なため、復帰を希望する女性をサポートする傾向があり、結果として、監督は男性が多いものの、ドワーフではプロデューサー5人のうち4人が女性だという。
松本氏によれば、ストップモーションはスタッフが物理的に一つのスタジオに集まるため、互いの実力や家庭の状況を把握しやすい。これが「正しい評価」と「親身なサポート」に繋がり、育児中のスタッフが時短勤務で復帰する際も、周囲が柔軟に対応できる土壌となっているという。ロールモデルのない小規模な業界だからこそ、自分たちで働き方を模索してきた自負を語った。
また、別の質問者からは、ベテラン女性スタッフの継続には「配偶者の地位や理解」が影響しているのではないかという、現場の肌感覚に基づいた問いが発せられた。
マージ氏は、ロサンゼルスの独立系スタジオの多くが夫婦による共同経営である実態を明かしつつ、同時にWIAが構築してきた「ウーマン・マフィア(女性たちの相互扶助ネットワーク)」の重要性を強調し、特定の個人や配偶者に依存するのではなく、志を共にする仲間が互いに引き上げ合うコミュニティ構築の重要さを示唆した。
最後に、21世紀に入り女性主人公の作品が増えた傾向と、今後の国際共同製作の行方について質問が及んだ。戸村氏は、「主人公が変わるのは、既存の価値観ではなく、少し先の未来を照らそうとする表現者の意志の表れ」であり、未来を捉えるには、マジョリティの外側に立つ「ストレンジャー」の視点が欠かせないと結論づけた。
松本氏は、国際共同製作を「料理」に例えて持論を展開した。「全てを同じ味にするのではなく、フランス料理や中華料理のように、それぞれの国やクリエイターのオリジナリティという『味』を尊重し、混ざり合うことが重要だ」と説く。特定の流行を追うのではなく、今の時代に自分たちが「面白い」と信じるものをピュアに追求し続けることが、アニメーションの国際的な未来を切り拓く唯一の道であると結び、シンポジウムを終えた。
登壇者の1人、マージ・ディーン氏の基調講演と独占インタビュー記事はこちら。