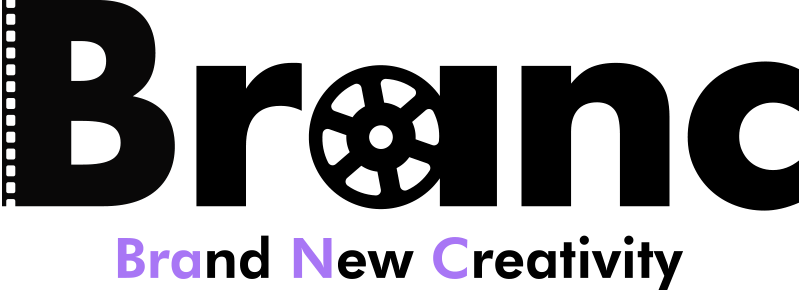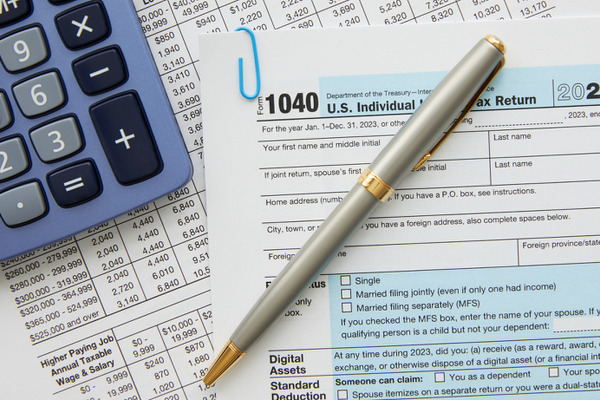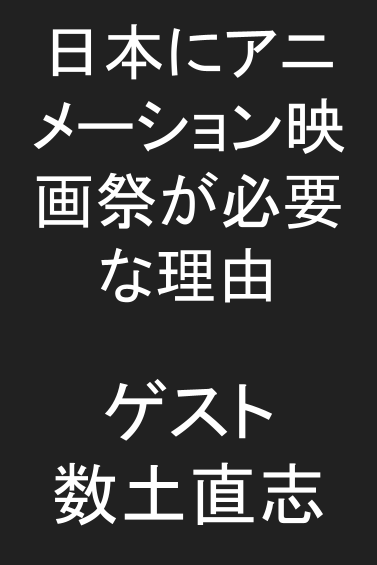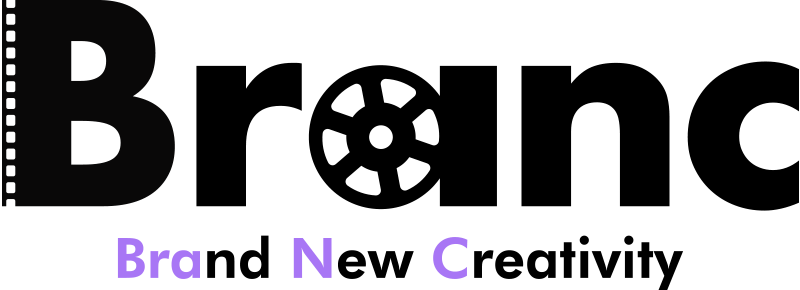映像クリエイターの祭典「VIDEOGRAPHERS TOKYO 2024」が開催。今年度は「OUT OF FRAME」をテーマに映像制作者を広く捉え、新たなヒントを提供する場として開催された。多くのトークセッションが催された中から、今回は海外で活躍する二人の女性クリエイターが登壇した「クリエイターとして生きる私たちー海外で見つけた可能性ー」のレポートをお届けする。
登壇者は、『SHOGUN 将軍』の編集を担当した映像編集者のAIKA MIYAKE氏、映像監督の中根さや香氏、MCは編集&ライター&プロデューサーの山本加奈氏が務めた。
海外に比べて日本の現場は女性が少ない
中根氏は、元々油絵をやっていたそうだが映像制作に転向し、現在は東京とロサンゼルスを拠点に活動している。近年では新しい学校のリーダーズのミュージックビデオ(MV)などを手掛けている。

AIKA氏は、元々日本のテレビ番組の編集者だったが、2010年にコマーシャル等のオフラインエディター(映像全体の構成を作る編集者)と呼ばれるポジションに移行し、2019年に渡米。編集は第二の監督と呼ばれるほど米国の映像業界では重要なポジションだと認識されているとのこと。

AIKA氏は真田広之主演の『SHOGUN』の編集にも参加、2話、5話、8話を単独で担当、9話、10話にも共同編集やアディショナルといった形で参加している。全部で19カ月ほどかかったそうだが、細かいディテールまで妥協せずに編集できる環境で毎日が楽しかったと語る。
『SHOGUN』の仕事はInstagramのDMからオファーをもらったそうで、Japan Timesの記事を読んだことがきっかけでプロデューサーが連絡してくれたのだという。そういったきっかけでつながりが生まれるので、アウトプットを意識しているそうで、『SHOGUN』のプレミア試写会にも正装で参加。前に出るのは苦手だそうだが、縁の下の力持ちのイメージがある編集の仕事のイメージを変えていくためにやれることをやっているそうだ。

自己紹介が終わり、トークテーマである海外での働き方が日本とはどのように異なるかについての議論が行われた。
AIKA氏は、日本での映像編集も楽しかったが、小さい時からハリウッド映画が好きで海外志向が強く、キャリアを積み、良いリールが作れる段階になって、米国のポストプロダクション会社にビザサポートしてもらえたという。その頃は#MeTooムーブメントの最中でその後押しも感じたようだ。日本にいた時から海外の人と仕事する機会も多く、代理店を紹介してもらったり、直接会いに行ったりなどの努力をコツコツと重ねていったそうだ。
中根氏の場合は、一度妥協せずに短編作品を制作。それは日本では評判にならなかったが、米国で拡がったことでチャンスが舞い込んだとのこと。

日本との違いについて、AIKA氏は、米国では男性だから・女性だからというしがらみがないと語る。シンプルにクリエイターとして最高の仕事をすることに集中できるという。「女性でいなければいけない」という空気感もなく、ただありのままの自分でいるだけで大丈夫な雰囲気があるそうだ。『SHOGUN』編集時に、男性プロデューサーから女性が目線で静かに伝える方がパワフルだと思うという理由で鞠子のセリフを減らしてみてはと提案されたが、AIKA氏は鞠子には自分の意思で台詞を喋ってほしかったのでショーランナーに直談判してカットしなかったという。
中根氏も、日本で働いていた時、現場に圧倒的に女性が少ないことが当たり前だと思っていたが、米国ではそうではなかったという。日本では女性が少ないことで委縮する時もあったが、今の米国は女性やマイノリティの進出が進み、仕事しやすくなっている。LAのプロダクションと打ち合わせをする時は、女性ではなく一人のクリエイターとして接してくれる、それは感覚的なことだが日本では感じたことがなかったそうだ。クリエイターが力を発揮するためには、そういう心理的な安全性が必要だと中根氏は語る。