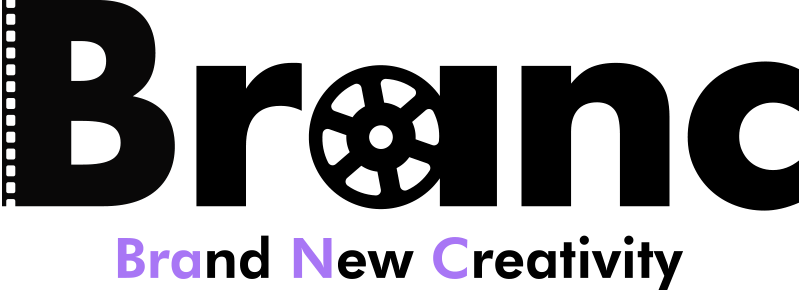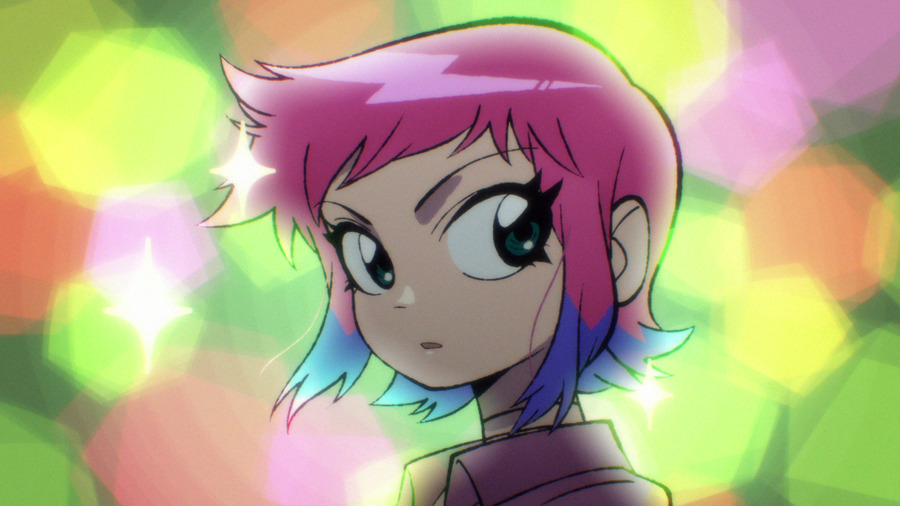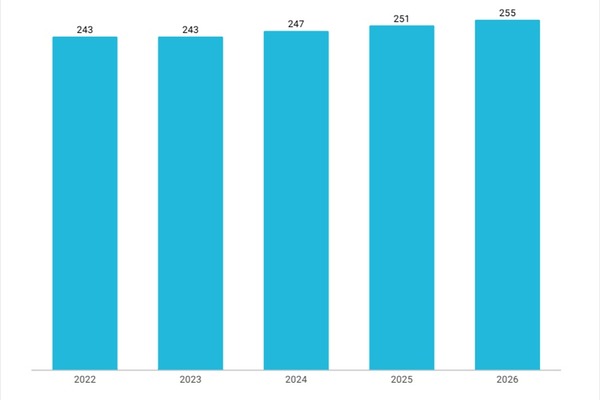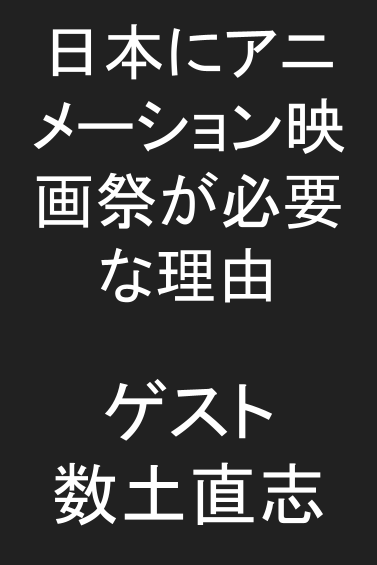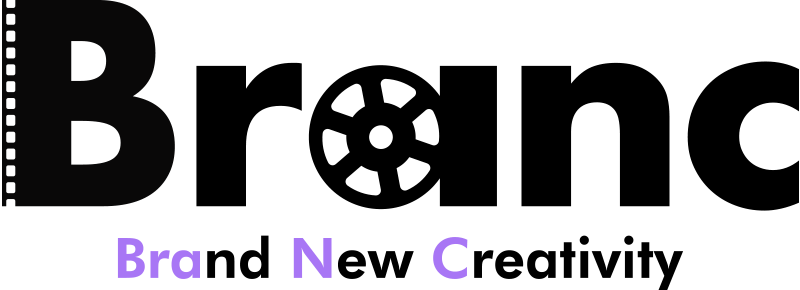©️2023 Universal Content Productions LLC
Netflixのアニメシリーズ「スコット・ピルグリム テイクス・オフ」は、『夜明け告げるルーのうた』や「平家物語」などで知られる日本のアニメーション制作会社・サイエンスSARU制作の作品だ。
だが、本作の原作はカナダのコミックで、2010年にエドガー・ライト監督によって実写映画化されている。熱心なファンがいることで知られるこの作品を日本でアニメ化したユニークな企画だ。しかも、原作とも映画とも異なるオリジナルストーリーが展開される。
サイエンスSARUはこれまでも「アドベンチャー・タイム」や「スター・ウォーズ:ビジョンズ」など、海外の企画に参加してきた実績がある。今回はどのように企画が実現したのか、国際共同製作ならではの苦労は何か、アニメーション・プロデューサーの崎田康平氏とアベル・ゴンゴラ監督に話を聞いた。

英語版と日本語版、両方を作る大変さ

――本作はその内容が面白いのはもちろん、海外コミックの原作、しかもかつて実写映画化された作品を日本でアニメにするということもユニークです。本作をサイエンスSARUさんが受けた経緯を教えてください。
崎田Netflixさんとは「DEVILMAN crybaby」や「日本沈没2020」などを一緒に作ってきました。その流れで次回作の企画会議の中でいただいたのが「スコット・ピルグリム」のアニメ化だったんです。弊社内にもエドガー・ライト監督の実写映画版と原作コミックのファンが多くて、制作チームを組めそうだったのでやることになりました。
――本作は日本法人のNetflix合同会社との企画ではなく、アメリカ本国のNetflixとの企画とお聞きしたのですが、割と珍しいケースではないかと思います。
崎田珍しいかもしれないですね。そうなった細かな経緯は、Netflixさんの中でもたくさん調整があったのだと思います。
――本作の脚本は原作者自ら手がけており、エグゼクティブ・プロデューサーなどもアメリカ人です。この国際共同制作をどう進めたのですか。
崎田お話をいただいたのが2年以上前で、プロダクション開始時にロサンゼルスに行って顔合わせをしました。向こうからはNetflixのチームの他、映画版を製作したユニバーサル・ピクチャーズの方、原作者のブライアン・リー・オマリーさんと共同脚本のベンデビッド・グラビンスキーさんが出席していました。ブライアンさんとベンデビッドさんがショーランナーの立ち位置で、クリエイティブな面で最後まで我々と一緒にやってくれました。脚本作業はその顔合わせ後に始まり、リモートでやり取りしながら作業を進めています。

――アベル監督はこの作品の話をもらった時に実写の映画は観ていたのですか。
アベルはい。大好きな作品でした。普通のハリウッド映画とは異なる雰囲気があって、3Dゲームや格闘ゲームの影響を強く受けた作風が面白く、またアニメ的な演出を取り入れているのも当時のハリウッド映画としては新鮮だったと思います。
――アニメ化に向いている企画だと思いましたか。
アベルそうですね。原作のコミックは平面的な絵でありながら表情豊かでアニメ向きだと思います。映画をそのまま再現するのではなく、どちらかと言うと原作を参照しています。映画版のネタはイースターエッグ(開けてからのお楽しみ)程度にとどめています。
――脚本は英語なので、それをまず日本語に翻訳し、絵コンテを作ってまた翻訳して米国側に確認してもらうという流れになるのでしょうか。
崎田そうですね。大きな流れとしては、脚本を翻訳し、絵コンテを作成してまた翻訳、それ以降の作業は英語と日本語の両方で進んでいたような形になっています。
今回の制作プロセスは非常にイレギュラーで、棲み分けを説明いたしますと、Anamanaguchiによる音楽制作と英語版の音声収録は米国で行い、絵コンテ以降の作画やダビング・ミックス作業は日本で担当しています。本作の主言語は英語ですが、今回はせっかく日本のアニメスタジオが作るので、日本語版も主言語の英語と同じくらいの扱いにして、日本語版の音声収録はこちらで行うという、2つのラインを動かすような形になっています。
――アニメ制作では、セリフに合わせて動きなどタイミングを測りますよね。その際、日本語と英語どちらの言語に合わせて演出したのですか。どちらを観ても全く違和感がありませんでした。
崎田まず脚本を翻訳して絵コンテを起こします。その後すぐにアニマティック(※絵コンテを元にラフな映像のかたちにしたもの)を作り、それをもとに米国でボイス収録をしてもらいました。その声をアニマティックに当てはめていってタイミングを決めて、作画を合わせていくという工程を踏んでいます。作画作業の前にユニバーサル側とフローを固め、そのような調整になりました。
翻訳ミスから生まれたアイデア

――本作は、原作とも映画版とも異なる展開ですが、脚本に日本側の意向はどの程度含まれているのですか。
アベル脚本の作業前に構成案を話し合う機会がありました。その段階でこちらからも色々な案を出し、脚本に反映してもらっています。その後も脚本の改訂作業の度に議論して共同で作り上げました。こちらの制作作業の中から出てきた新しいアイデアも採用されています。例えば、忍者の恰好をしたパパラッチが出てきますよね。あれは元々翻訳ミスから生まれたものなんです。
――国際共同制作ならではのアクシデントですね。どのような状況で発生したのですか。
アベル当初、米国側は普通のパパラッチをイメージしていたようですが、こちらからラフ案を送ったところ、「もっとニンジャっぽい感じで」というフィードバックをもらったんです。「ニンジャっぽく」だったところを、猿飛佐助のような本当の忍者のデザインにしてしまい、それを送ったら向こうはビックリしながらもそれが気に入ったようで、パパラッチがあのデザインになったんです。それから、最後に登場する年を取ったスコットもこちらから提案したものです。
――日米共同の企画を監督する立場として、どんな点に苦労がありましたか。
アベルやはり普通のアニメ制作とは違う形になったので苦労は多かったです。しかし、米国側も普段のやり方と異なるプロセスだったと思います。どちらの立場から見ても普段と違うやり方をしたので、私やプロデューサーはその両者の間に立ち、時には両方を説得しなければいけないこともありました。
たとえば、カッティング作業は日本の場合、一度で終わることがほとんどですが、今回は米国側のフィードバックに合わせて数回行うこともありました。通常ない工程をはさむことにより、演出陣を苦労させてしまったと思います。
クリエイティブの主導権を握るために粘り強く交渉

――クリエイティブのコントロールをめぐって、米国側とどのような話し合いをもたれたのでしょうか。
崎田アベル監督が言ったように、米国側からの要望・意見はたくさんありました。我々が一番大事にしたことは、クリエイティブの最終判断は監督にあるということです。この演出家はこういうことが得意なのでこのエピソードを任せたいとか、ここを膨らませたいとか逆にここはカットしても成り立つなど、全体の判断は監督がジャッジするということは念押ししました。もちろん、向こうにも言い分はあるので、何往復もやり取りすることになるんですが、最終的にアベル監督が納得できるものにするために粘り強く交渉しました。
――実際に完成作品を観たエドガー・ライト監督や原作者のブライアンさんはなんと言っていましたか。
アベルみなさん満足してくれたようです。おそらく当初は向こうがクリエイティブの主導権を握りながら進めるイメージを持っていたのではないかと思います。しかし崎田さんが言ったように、日本のアニメ制作の演出の役割、演出担当にある程度自由を与えないといいものにはならないなど、丁寧に説明する必要がありました。米国の場合、こういう企画ではほぼ脚本通りに作られていくことが多いと思いますが、日本では絵作りの段階で演出の意向で膨らませることがあります。そうした日本のクリエイティビティで完成した作品に対して、最終的にはそのやり方で良かったと思ってくれたようです。
――主導権を保つためにたくさんの駆け引きがあったわけですね。サイエンスSARUさんはこれまでも国際的な企画を実現させてきた分、そういうやり取りにも慣れているのでしょうか。
崎田そこは、弊社代表のチェ・ウニョンが頑張って守ってくれている部分が大きいと思います。現場のスタッフはやはり日本でアニメ作品を作っていますから、その良さを守るためにも請負仕事にしたくありませんでした。
――サイエンスSARUさんは、こうした国際的な企画を手がけることが多いですが、それは意識してそうされているのでしょうか。
崎田新しいこと、変わったことに挑みたいスタッフが多いという特徴はあるかなと思います。アベル監督も代表のウニョンもそうですし、色々な国からスタッフが集まっているのが弊社の特徴でもあるので、こういう企画を前向きに検討しやすいのかもしれません。
――こうした国際的な取り組みによって、日本のアニメ業界にどんな影響を与えることができると考えますか。
アベルこうした企画を成功させることで、アニメ業界全体にユニークなオファーが増えるんじゃないかと思っています。
崎田大それたことは言えないですけど、国際的な企画は大変な面もありますが、それも含めて得難い経験になると思います。海外の価値観で考えるクリエイティビティに触れると現場にも刺激があるでしょうし。日本のIPに限らず色々なことに挑戦したいクリエイターは国内にもたくさんいると思うので、そういうものに挑み続けるマインドを持ち続けたいですね。
Netflixシリーズ「スコット・ピルグリム テイクス・オフ」はNetflixにて世界独占配信中。(全8話)