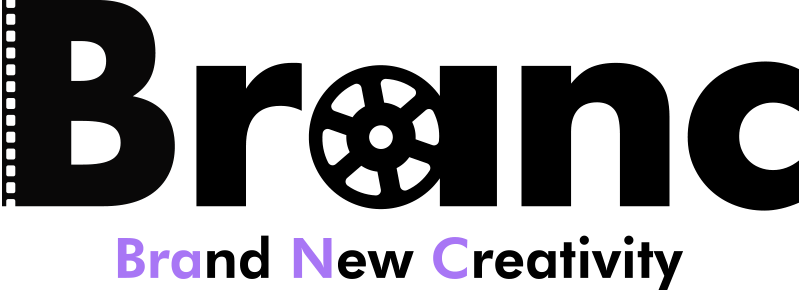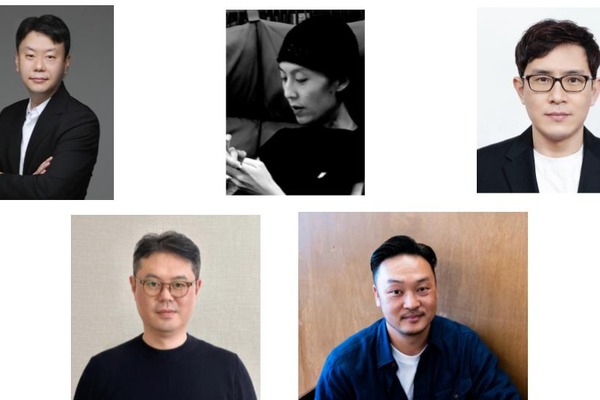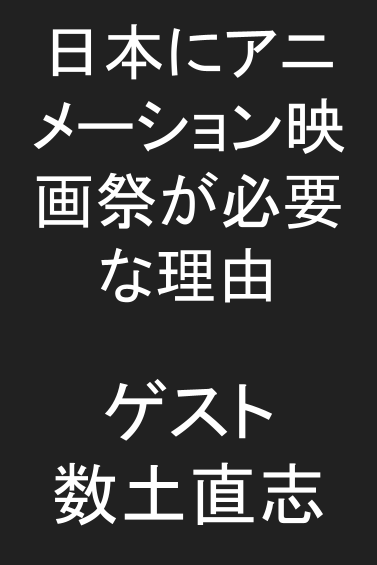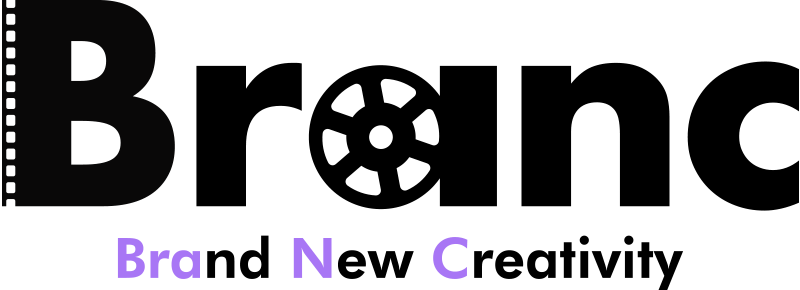2021年に公開された『猿楽町で会いましょう』で注目された児山隆監督の長編映画2作目となる『万事快調〈オール・グリーンズ〉』が、2026年1月16日に公開された。
原作は、第28回松本清張賞を受賞した波木銅氏の同名小説。舞台は茨城県東海村。閉塞感の漂う地方都市で、ラッパーを夢見る朴秀美、スクールカースト上位ながら家庭に問題を抱える矢口美流紅、そして毒舌で斜に構えた岩隈真子。本来交わるはずのなかった3人の女子高生が、「一攫千金」を狙ってある禁断のビジネスに手を染めていく様を描いた青春映画だ。
主要キャストには南沙良、出口夏希、吉田美月喜という若手実力派が顔をそろえている。
Brancでは、本作が正式出品された釜山国際映画祭で、児山監督にインタビューを実施。作品に込めた想いを聞いた。

荒っぽさと知性を併せ持った物語
――本作の制作の経緯からお聞かせください。
児山:2023年の5月頃だったと思います。近藤多聞プロデューサーから、「映画化の企画を進めているから」と原作を読ませてもらったのが始まりです。
――児山監督は、原作を読んでどんな印象を持ちましたか。
児山:誤解を恐れずに言うと、「荒っぽいのに知性がある」と感じ、そのアンバランスさが面白かったです。読み終わってすぐに、これは映画化したいという衝動に駆られましたね。荒っぽいというのは、未熟や粗削りということではなくて、過激というのともちょっと違う。「荒っぽい」としか言いようがないんですけど、原作の持っている本質的な部分にそう感じたんです。
――原作小説を映画化するにあたり、エピソードの取捨選択も必要だったと思います。実際、削られたエピソードもありますが、どんな基準で映画を構成したのですか。
児山:まず、この映画にとってどういう構造が適切かを考えました。小説は3人の女子高生視点を中心にして、モノローグを含めて進行していきますが、それ以外の視点もあって、全部やるには毎回主役が変わる深夜ドラマのようにしないといけない。それはそれで面白いかもしれませんが、2時間の映画の場合は視点を集約した方がよいと思ったので、朴秀美の視点で物語を進めていくことにしました。
その上で、原作の切れ味するどい会話劇は持ち味ですが、会話ばかりが続くと、物語を進めにくい部分があります。けれど、そういう会話の応酬が面白い作品でもあるので、それも大事にしようと思いました。読んでみて、この物語は観客をどこかに連れて行ってくれるような作品だと思ったので、映画ではクライマックスにより大きな盛り上がりを作ることにしました。

――原作よりも、中心となる3人の女子高生にフォーカスする内容になっています。夜の交差点で子連れの女性と出会うシーンがそれを象徴していますね。原作では秀美だけが居合わせたあの場に、3人が居合わせるように変更されています。
児山:映画の企画が始まり、シナリオハンティングで東海村に行った時にあの交差点を見つけました。まず、彼女たちがどんなプロセスを辿って、結末を迎えるのかを示唆したかったので、同じ経験をさせたいというのがありました。あの3人は、相容れない部分があるわけで、それでも一緒に何かを成し遂げようとするのなら、強制的な共通体験があったほうが説得力が出ると思ったんです。
青春を通して東海村の問題も見えてくる
――交差点のシーンは東海村での撮影なんですね。ロケ場所は東海村が多かったのですか。
児山:学校は別の場所にありますし、家の中のシーンも違いますが、ロケは大体東海村ですね。「東海村には何もない」というグラフィティが出てきますが、あれも実際にあるものなんです。ロケハンで見つけて、使おうと思いました。
東海村は画になるロケ地が多かったと思います。それにとても撮影に協力的でした。役場の方に、存分にやってくださいと言っていただいて、いまだに連絡をとりあっています。

――女子高生が大麻を売る話なのに、歓迎してくれたんですね。
児山:それは僕らも心配だったので事前にお聞きしたんですけど、それでもいいと言ってくださったんです。村長も色々なことにチャレンジしたいんだと言っていて、とても話のわかる方でした。
――東海村は、よく知られているように原子力発電所がありますが、そうした村の背景をどの程度入れていこうとお考えでしたか。地域特有の社会事情を背景にした青春ドラマという印象を受けました。
児山:おそらく僕自身がティーンエイジャーの頃、正直言ってそんなに世の中のことを重大に捉えていなくて、社会問題もあまりよくわからなかったですけど、その場所に暮らしている若者から見えてくるものって、あると思うようになりました。
東海村には原発があって、それは象徴的なものではあるんですが、それだけじゃなく、日本の地方都市が抱える問題がいくつもあって、それが彼女たちを通して、見えてくる気がしました。ただ、それを明確に社会批評的なことに結びつけるつもりもなくて、彼女たちの青春を描いていけば、それはおぼろげに見えてくるはずだと考えています。原作小説もそういうスタンスで書かれていると思うんです。
――本作は様々なサブカルチャーが作中で言及されます。このあたり、監督はどのように捌こうと思いましたか。こういうのはやりすぎてもクドい感じになりますよね。
児山:この作品をやるからには避けては通れないし、面白い部分でもあります。心掛けたのは、観客がタイトルを知らなかったとしても、作劇が止まらないことですかね。知っている人はニヤリとできるくらいの感じで、知らなかったとしても話は理解できて、面白いと思ってもらえることを大切にしました。

目指したのは「落伍者の青春物語」
――釜山国際映画祭に参加された印象はいかがですか。
児山:7,8人の方にサインくださいと言われて、面白かったと言ってもらえて嬉しかったです。若い人に伝わるか不安だったんですけど、若い世代の観客が多くて、きちんと刺さったみたいです。
これは釜山という街が映画文化を育んできたからなのかもしれないですね。映画をすごく大切にしてきた街なんだなって実感します。
――東海村のローカルな物語が、韓国の釜山の若者にも届いたというのは、監督の中で自信につながりましたか。
児山:そうですね。面白くなると信じて作っていましたが、この手の作品は作り手だけが盛り上がってしまう危うさもあります。独りよがりになっていないか怖さもありましたが、韓国のお客さんに受け入れられてホッとしました。国際映画祭なので、韓国の方だけでなく、60代のタイの方も見てくださって、褒めていただき本当に嬉しかったです。
――鬱屈した若者の物語は、世界的に共通ですね。
児山:そうですね。でもこういうタイプの青春映画はこれまでなかなかなかったと言ってもらえました。例えば、僕は高校の時に『SLAM DUNK』を読んで絶望したわけです。青春ものには、ある種の残酷さもあると思うんです。ああいう青春を謳歌できる人はいいけど、謳歌できない人に対して、失格と言っているような。インターハイに行けて涙を流すキャラクターを見ながら、自分は行けてないよなって思ってしまうんです。だから、僕としては落伍者の青春物語を作りたかったというのはあります。
――そんな落伍者の青春を体現するキャスティングについてはどういうことを大切にしましたか。
児山:最初に決まったのは、秀美役の南沙良さんです。全員に言えることは、フレッシュであってほしいということですね。やっぱり青春映画ですから。以前にも見たことあるなと感じてしまうと、一瞬の刹那の感じやきらめきが失われてしまうと思ったので、これまで演じたことのない役柄に挑戦してほしいと考えました。
――確かに、南さんのこういうタイプのキャラは新鮮ですね。ドカッと足を開いて座る感じとか、すごく様になってるなと思いました。
児山:あれも僕が足を開いて座ってほしいと指示したわけじゃなくて、彼女が自然にああいう芝居をしてくれたんです。秀美はまだ高校生なので、あの世代特有の「カッコつけたい感じ」が要所要所で出てしまうキャラクターなんですよ。南さんは、クールさとそういう幼さが同居している芝居をしてくれたと思います。

――秀美以外の2人、美流紅と岩隈はどうでしょうか。
児山:美流紅は、クラスにいる人気者という感じでみんなに好きになってもらいたいと思っていました。こういう人にクラスで話しかけられると嬉しいみたいな感じをだしたかったんです。出口夏希さんの持っている魅力がそれを可能にしてくれたと思います。

岩隈は、僕以上に臆病な人で、会話するのも得意じゃない。だから美流紅みたいな人に引っ張られてしまうんですね。吉田美月喜さんはその部分を的確にアプローチしてくれました。眉毛を整えていないとか、トリートメントしてないとか、体がいつも強張っていたりと、外的なものと内面的な両方から上手くアプローチしていました。

――最後にこれから作品をご覧になる方々にメッセージをお願いします。
児山:自分もひねくれている方だと思うんですが、そういう人にとって面白いものが出来たと思います。自信を持って見に来てほしいと言える作品になりましたので、是非劇場にお越しください。