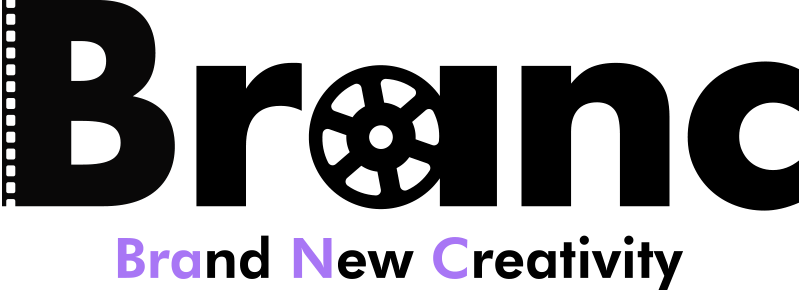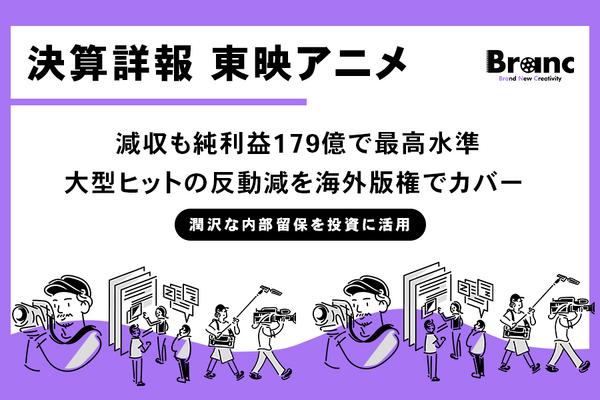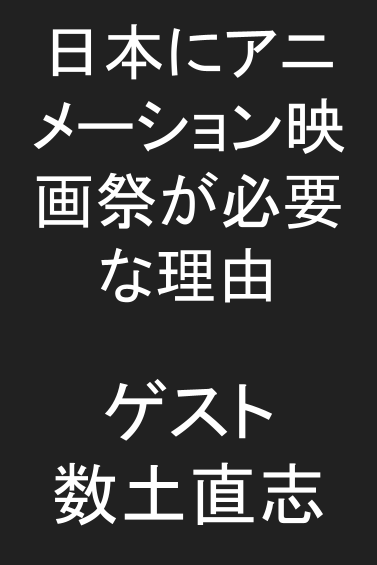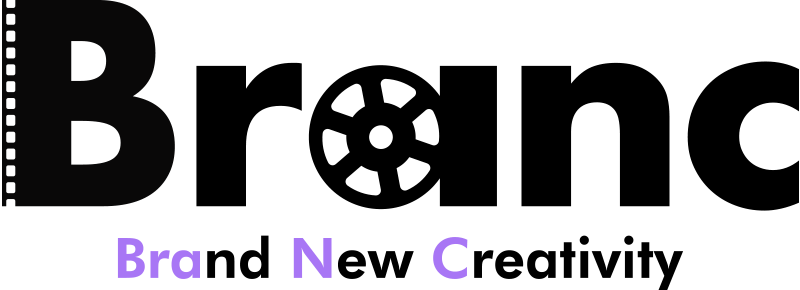昭和から平成にかけて人気を博した「あぶない刑事」シリーズの最新作、『帰ってきた あぶない刑事』が5月24日から公開される。
1986年10月に始まったテレビシリーズからはじまり、今年で38年目を迎える同シリーズ。前作『さらば あぶない刑事』で完結と思われたが令和の時代となっても復活することとなった。
これだけ長期にわたってシリーズが継続した原動力は何か、そして今の日本の映画産業における課題など、同シリーズに長く関わり続けたプロデューサー、近藤正岳氏に聞いた。

『あぶない刑事』シリーズが長く続いた要因

――前作『さらば あぶない刑事』の後で、なぜまたシリーズを復活させることになったのでしょうか。
前作は最終章のつもりで作っていましたが、「さらば」の記者会見の時に司会の方が「これで本当に終わりですか」と質問したら、柴田恭兵さんが「当たればまたすぐ戻ってきます」とも言っていました。柴田さんの言葉は半分ジョークだったと思いますが、実際に当たってしまったわけです(笑)。
それから、セントラル・アーツの黒澤満社長も存命の時、ヒットしたので良いタイミングでまたやりたいねという話はしていました。『さらば』でタカとユージがニュージーランドに旅立ったけど長続きしないだろうから、横浜で探偵事務所を開くというストーリーはどうかと、そんな話をしていたんです。
――近藤さんと黒澤さんの中では構想自体は前作の直後からあったのですね。
いつ公開するとか具体的な構想ではなく、あくまで与太話のレベルですけどね。でも、映画ってそういう他愛のない話から生まれることがあるんです。2018年に黒澤さんが亡くなって、セントラル・アーツもプロダクションとしては休止状態になってしまったんですけど、せっかく老舗の看板タイトルがあるならもう一度製作を再開すべきではという話が東映からも出まして、僕個人としても黒澤さんから宿題を残されたような気持ちもあったので、物語を具体的に考え始めて舘さん柴田さんに相談したのが2020年の最初の頃です。その直後にコロナで撮影もできない状態になって、この企画も止まってしまったんですが、なんとか完成させることができました。
――近藤さんはこのシリーズにずっと関わってこられたんですよね。
1作目の映画から制作宣伝で現場に関わっています。1996年『あぶない刑事リターンズ』の時は宣伝プロデューサー、企画としてシリーズに関わりだしたのは1998年の『あぶない刑事フォーエヴァー』からで、37年このシリーズと付き合っています。
――このシリーズがこれだけ長く続いている原動力は何だと思いますか。
時代ごとに、『あぶない刑事』を作りたい人が現れるんです。昭和から平成にかけての映画3部作は、テレビドラマのヒットで生まれました。最初のテレビドラマは2クールの予定でしたが、それが1年に延長されて、映画も視野に入れた展開となり、その映画が大ヒットを記録した。当時はあまり当たると思っていなかったので、ジャッキー・チェンの『七福星』と同時上映だったんです。同時上映でもパンフレットの売れ行きでどっちが人気あったのかわかるんですね。ふたを開けてみれば『あぶない刑事』の方が圧倒的にパンフレットが売れていました。それでさらに映画を2本、テレビシリーズも第2シーズンが作られていきました。
――89年まで継続的に展開してきたシリーズが一旦途切れて、90年代半ばに復活しますね。
はい。96年の映画『あぶない刑事リターンズ』が作られたのは日本テレビからのオファーによるものです。これはテレビシリーズの夕方の再放送が視聴率も良かったことで企画されました。98年の『あぶない刑事フォーエヴァー』の映画とテレビのメディアミックス展開も日テレ主導で企画されました。
――90年代は日テレ主導で企画され、2000年代になると、また変わっていくわけですね。
黒澤さんから「ぼちぼち、もう一回やろうか」という話がでて、セントラルアーツの企画で2005年に『まだまだあぶない刑事』ができました。それから、『さらば あぶない刑事』を2010年代に作ったわけです。
シリーズを振り返ると、例えば、最初のテレビシリーズ最終話では幽霊が犯人のエピソードがあったり、結構無茶な設定もやってきたんです。ハードボイルドなだけじゃなくて、コミカルなパートも多いし、冒険が許される作品だったことが人気を支えたんだと思いますし、すぐ量産するんじゃなくて時代の節目ごとに作りたいと言う人がちょうどよく現れるのが、消費され過ぎずに済んだ要因かもしれません。
――長いシリーズ展開で横浜を撮り続けていますが、街の変化の大きさを実感しますか。
相当変わりましたね。みなとみらいでも撮影しましたが、あの辺りは昔は埋め立てたばかりで本当になにもなかったですからね。
――今回はロケ地マップ作りで横浜市とコラボしています。
はい。前作の時は横浜市の対応が公開終了後になってしまいましたが、今回はすごく早い対応ですでにロケ地マップを作ってくれていてありがたいですね。赤レンガ倉庫などはテレビシリーズのエンディングの撮影に使用したことで有名になった面もありますし、倉庫としての役割を終えた後も保存することになったことにも、このシリーズが多少は貢献していると思うんです。
若手の原廣利監督抜擢の理由

――今作は、若手の原廣利監督を起用しています。本テレビシリーズの1作目で監督を務めたこともある原隆仁さんのご子息というつながりはありますが、どういう経緯で抜擢されたのですか。
実はこの作品は単体の企画じゃなく、タカとユージがニュージーランドにいる間、町田透を主人公にしたスピンオフの企画もあったんです。タイトルは「そこそこあぶない刑事」というもので、その後にタカとユージが帰ってくる作品をやろうという構想でした。いわゆる「あぶ刑事」サーガみたいなものを作ろうと思い、『そこそこあぶない刑事』はフレッシュな若手監督にやってもらおうと考えて、原廣利監督にお願いしようと思っていたんです。
でも、結局その企画は流れて、今作の監督をしてもらうことになりました。彼のお父さんとは僕が宣伝担当時代に『べっぴんの町』という作品でご一緒した縁もあったし、テレビシリーズ1作目で監督もしている人だから、『あぶない刑事』が世代を超えて繋がっていく要素がスタッフにあっても面白いかなと思いました。
――若手監督に撮らせて若い世代にもアピールしようという狙いもありますか。