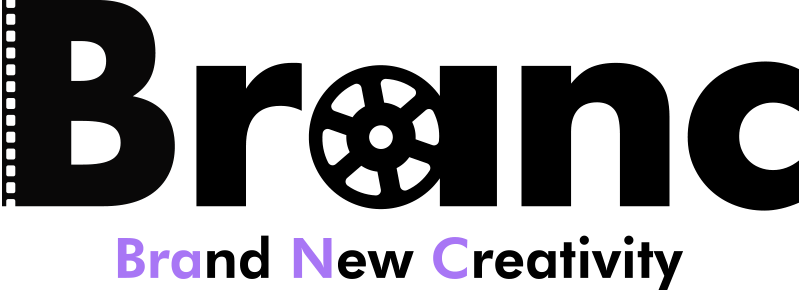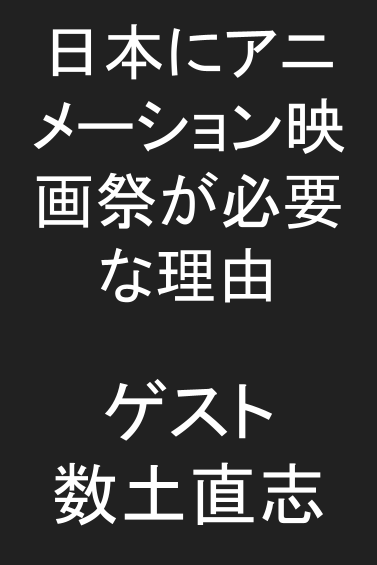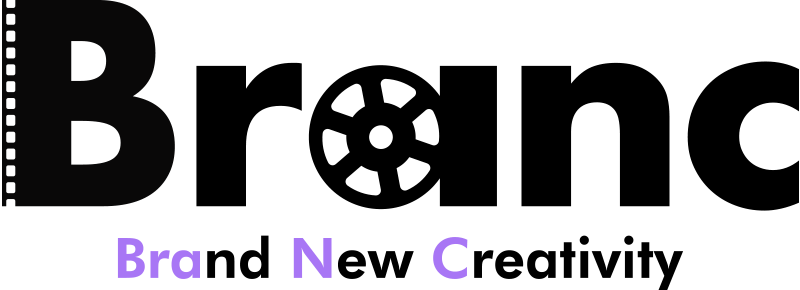Photo by:Jumpei Yamada
Branc(ブラン)編集長のmarindaが若手業界人とラフにおはなしする「【Next-Gen】若手業界人とおはなし」の第二弾。
本企画はBranc編集長のmarinda(現在26歳)が同世代の若手業界人とラフに近い目線でお話していく企画。今年9月で立ち上げ1年となったBrancの日々の成長や悩みと共に、新しいことにチャレンジしていく次世代【Next Generation】の若手の映像業界人と意見交換をしていく。
第二弾は2022年に「NOTHING NEW」という映画会社を立ち上げた林健太郎さん、鈴木健太さんとおはなし。映画会社として立ち上がった「NOTHING NEW」はレーベル初のプロジェクトとして、VHS喫茶「TAN PEN TON」をオープンした。

「TAN PEN TON」は世界中から厳選されたショートフィルムのVHSをブラウン管テレビで楽しむことができる喫茶店で、下北沢 BONUS TRACK内に10月12日(木)にオープン。代々木上原の人気カフェバー「No.」出身のディレクターとバーテンダーが手がけるフード・ドリンクとともに、NOTHING NEWがセレクトした世界中のショートフィルムの鑑賞や、喫茶店での交流を楽しむことができる。オープンにあたりMotion Galleryに掲載されたクラウドファンディングでは、341人の協力を集め、目標金額400万円を上回る形で達成した。
映画会社初のプロジェクトにフィジカルな場づくりを選んだ理由、ふたりが描く映画業界の未来像など、広く歓談した。

“答えのない問い”に挑もうと思ったきっかけ
――まずはおふたりのご経歴を教えてください。
林新卒で映画会社に入社し、5年ほど映画の企画開発・劇場勤務などをしていました。その中で、同世代や次世代の才能あるクリエイターと一緒に作品を作ったり、海外に挑戦したりしていきたいという想いが強くなりました。その後、その想いを実現するためには、映画業界の課題に0から本腰を入れて向き合う必要があると気づき、2022年4月にNOTHING NEWを立ち上げました。
鈴木僕は10代の頃からアニメーション作品や自主映画を作っていました。その後、多摩美術大学を中退してミュージックビデオや映像のディレクターを経験し、今は広告会社で企画もするようになりました。そんな中、ふとしたきっかけで林くんと出会いました。もともと僕は子どもの頃から映画を作りたいと思っていたんですが、その時に自分がクリエイターとして感じていた課題と林くんの日本の映像・映画業界に対する「もっとこうした方がいいのにな」という想いがマッチしたんです。そこで、一緒にやってみようと会社を立ち上げて、1年以上経ちました。作品やプロダクトは目下準備中なんですが、最初のプロジェクトとして「TAN PEN TON」というお店が立ち上がりました。
――おふたりが出会ったきっかけや、お互いが共鳴できた部分はどんなところだったのでしょうか?
林コロナ禍の緊急事態宣言直後に「劇団ノーミーツ」というオンラインで創作するストーリーレーベルを始めたんです。そこでは当初、"一度も会わずにリモートで創作する"をコンセプトに、SNSへZoomを使った演劇動画を投稿していたんですが、リモートでの創作の可能性を更に追及すべく、生配信の有料公演『門外不出モラトリアム』に挑戦することになりました。
そこで、SNSで繋がっていたスズケン(鈴木さん)に予告編制作を相談したのが出会ったきっかけです。結局は予告編に限らず、スズケンが広くクリエイティブで関わりたいと言ってくれて、その後もひたすら一緒に創作活動をしていました。なので、出会いは3年くらい前ですね。
鈴木林くんは創作活動に対する視座が高く、クリエイターが活躍するための場づくりに対して色々な課題感を強く持っているんです。それはまさに今の日本の映画業界・映像業界の課題と直結する部分だと思いました。僕自身もクリエイターとして生きていく上で、日本の課題を解決しないとこれからの未来は良くならないし、面白くならないと思っていました。20代のうちに一緒に何か始めたいなって思っていたので、林くんの想いに僕も乗っかっていきました。
――コロナ禍での創作活動が今のプロジェクトに繋がっているんですね。
林コロナ禍になって、例えば映画業界で言うとミニシアター・エイド基金など、クラウドファンディングをして金銭的に支援する動きがあって、自分も賛同して協力していました。それがとても意義のある活動だと思う一方で、当時は「もしコロナ禍が永久に続くとしたら、一時的な金銭的支援と同時に、いまからその環境で創作活動を続ける可能性を探っていかないと、クリエイターや役者を取り巻く環境が持続的になっていくことが難しいんじゃないか」と思ったんです。そんな答えのない問いに挑み続ける場であったのが、ノーミーツでした。
活動をしていく中で、若手クリエイターやインディペンデント作品で良い人材・作品はたくさんあるのに、なぜそういう人や作品が商業的に脚光を浴びる動線が少ないんだろうと業界の構造に対して疑問を持ち始めたんです。ノーミーツで答えのない問いに一緒にチャレンジしたスズケンとだったら、きっと映像業界の課題解決にも挑んでいけると思いました。
数年後の映画業界のために今挑戦したい
――インディペンデント作品や作家に対する課題で、具体的に変えたいと感じるのはどんなところでしょうか?

鈴木オルタナティブな表現こそが未来の映像文化を切り拓いていくと思っています。だけど、それを突き詰めていく人たちをおもしろがる土壌が少なく、彼らが大きなステージを目指していくためのルートも見えにくいと感じています。
――クリエイターがキャリアアップしていくイメージが湧きにくいというか……?
林そうですね。今、映画監督や映画プロデューサーなどを志す若者って、果たして何人いるんでしょう……。正直、大きな夢を抱きづらい、イメージしづらいのが映画業界の現状だと思っています。作品の規模に限らず評価される環境があって、日本で成功したら海外に進出できて、金銭的にも夢があって……という動線が今の日本映画業界には存在していません。もちろん監督個人や作品単体での成功事例はありますが、そのほとんどが個人で開拓したルートによるものであり、日本の機関や企業による持続可能なシステムはあまり介在していません。
今、マンガや音楽の領域は、次の世代にどう繋げていくかという議論が業界全体でなされていて、未来へのポジティブな流れを感じます。だけど、映画業界ではそもそもそのような議論が少ない印象です。課題は山積みですが、まずは未来に向けた意見を交わし、業界全体で連帯していく動きを積み重ねることで、いずれ社会を巻き込んでいくムーブメントに繋がると信じています。自分たちはまだ小さなチームですが、少しでもその動きを加速させる力になりたいです。
――ありがとうございます。既存の映画業界を変えていきたい気持ちをおふたりから感じます。
林作品単位だけではなく、映画業界の未来を中長期のレンジで考える視点は、もっと持たれるべきだと思いますし、自分たちも挑戦していく上で一番大事にしています。
鈴木音楽だと常に新しいシーンが生まれ、そこに人が集まってくるような流れがあったり、アート文脈ではアーティスト・イン・レジデンス(※)のような仕組みが作り手の場になったり。だけど、日本の映画にはあまりそういうシーンが生まれてくる土壌がなく、とくにユース発というのは本当に少ない気がしています。そういったシーンを生み出す一手として、TAN PEN TONのような場が小さくとも必要だと感じ、作りました。僕らがやりたいのは既存の業界構造を壊す・変えるというより、別のルートや場所を開拓するイメージです。
※アーティスト・イン・レジデンス:国内外からアーティストを一定期間招へいして、滞在中の活動を支援する事業
――ここまで、「海外」というワードもおふたりから多く出てきましたが、グローバルという場に日本のクリエイターが挑戦するために必要なことは何だと思いますか?

林一番っていうのが難しいところなんですけど……先日初めてプチョン国際ファンタスティック映画祭のマーケットに行きました。同世代の他の国の人たちは、みんな英語が喋れてプレゼンができて、企画にも自信があって……とてもエネルギッシュに感じられたんです。20代の監督やプロデューサーが自分たちの口で企画をプレゼンしていくのを目の当たりにして、日本のクリエイターは語学や海外へ挑戦する意識において、まだ壁があると思いました。
一方で、自分たちの企画自体は各国のプロダクションから評価も頂き、そのハードルさえ乗り越えられれば海外で勝負ができる可能性も感じています。日本は海外でルートを広げていくための環境も他国に比べて整っておらず、業界内で情報共有をしていくカルチャーもまだ根付いていません。だからこそ、NOTHING NEWとしては海外を視野に入れて活動していき、海外を目指すクリエイターの架け橋になりたいです。
ショートフィルムから出会ってほしい

――NOTHING NEWの初の取り組みとしてVHS喫茶のTAN PEN TONが生まれたと思うのですが、プロジェクトの第一歩に“場作り”というところを選ばれた理由を教えてください。
林ひとつ「NOTHING NEW」としての場を作り、そこにやってくる人々の交流を経て、自分たちのブランドや価値観を知り、興味を持ってもらいたいと思ったのがきっかけです。これまで、映画作品を届けるために宣伝を行なっても、毎回公開が終わると作品自体の発信が終了し、それまで繋がっていた方々との関係性が一度切れてしまうことにとてももどかしさを感じていました。作品を手がけているレーベル自体が発信していく場を持つことで、ある作品に興味を持ってもらえた時に、その作家をより深く知ったり、NOTHING NEWの他の作品にも興味を持ってもらうきっかけに繋がるのではないかと思いました。
鈴木「TAN PEN TON」はVHS喫茶と銘打っているんですが、コアなコンセプトは「ちいさな映画の発信拠点」です。世代を超えて気軽に映像作品に触れられるハブとなって、ショートフィルムや才能をキュレーションしていきます。例えば、店の前をたまたま通りすがった高校生がVHSを手にして、観たことのない作品を知るとか、今まで映画に接点のなかった人たちが参加してくれるような場所にしたいです。TAN PEN TONの「TON」は「屯(たむろ)」という言葉からとっているんですが、場を生み出した僕たちが権威になるのではなく、作品も世代も関係なく色んな国や人のものがふらっと集まって“たむろ”する、気軽な場として存在したいという想いがあります。
――TAN PEN TONで“ショートフィルム”に特化したのはどういった理由があるのでしょうか?
林「まずはショートフィルムをもっと多くの人に知ってほしい」という想いが一番にあります。作り手側の視点で言うと、短編作品は長編作品よりも作る上でのハードルが低く、挑戦しやすい一方で、展開する出先が限られている課題があります。また、観る側の視点だと、そもそもショートフィルムの認知自体が広がっていないのが現状です。正直、自分たちもショートフィルムに注力すると決めるまでは、こんなにたくさん素敵な作品が存在していることを知りませんでした。
僕たちのお店きっかけでショートフィルムの存在を知ってもらい、他のショートフィルムを観てもらったり、さらに作家さんを深掘りして知っていただいたりする場にしていきたいです。ショートフィルムの面白いところは、ジャンルを越境してコントやMV、アート展示の作品など色々なカルチャーと接続できることだと思うので、映画に限らずそういった作品も徐々にラインナップに加えていきます。
――最初はどんな作品が観られるようになる予定ですか?

鈴木ヨーロッパ企画の上田誠さんの過去作や、MVディレクターPennackyさんの制作作品、アニメーション作家の若林萌さんの作品などをVHSにしました。作品のジャンルも世代も国もバラバラで、これから実験的な作品も多く増やしていきたいです。せっかくリアルな場を用意するので、観るだけではなく、VHSという物理メディアで作品を“選ぶ”ことも楽しんでほしいんです。なんならちょっと作品選びに失敗した……みたいな経験すら愛おしくなってくると、新しい世界が広がっていくことが楽しくなるんじゃないかなと。サジェストされたものではなく、自発的にショートフィルムを選んで観るという体験が受け手の鑑賞態度や意識も変えられるといいなと思っています。