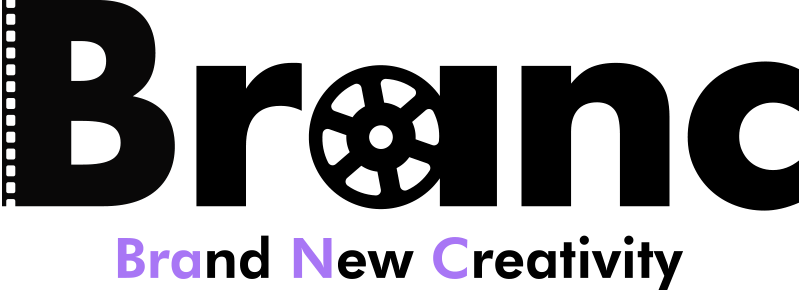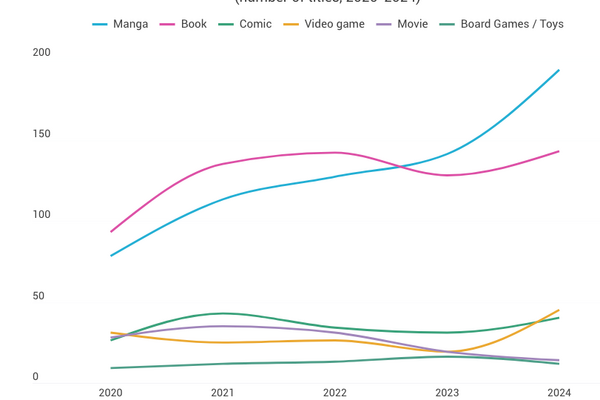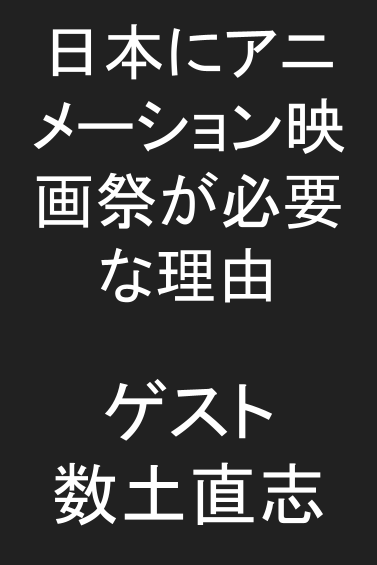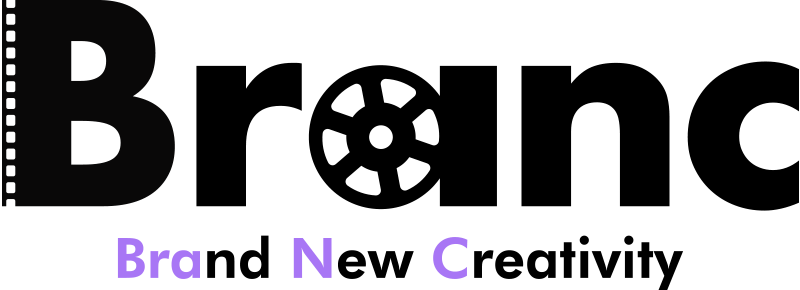米南カリフォルニア大学(USC)アネンバーグ・インクルージョン・イニシアチブは2023年1月、2007年から2022年までの北米興行収入上位1,600作品における監督のジェンダーおよび人種・民族に関する調査報告書を発表した。
同大学のデータによると、2022年のトップ映画における女性監督および人種的マイノリティ(Underrepresented)の監督の割合は、前年と比較して減少しており、ハリウッドにおける多様性の推進が停滞、あるいは後退している現状が浮き彫りとなった。
報告書によると、昨年、興行収入上位100作品を作るために雇われた111人の監督のうち、女性監督は2021年の12.7%から減少し、わずか9%という結果になった。同時に、黒人、アジア人、ヒスパニック/ラテン系、多人種・多民族系の映画監督も2021年の27.3%から2022年には20.7%に減少している。特に「有色人種の女性(Women of Color)」の状況は深刻である。2022年の上位作品でメガホンを取った有色人種の女性はわずか2.7%(3名)であった 。この3名は、『ウーマン・キング 無敵の女戦士たち』のジーナ・プリンス=バイスウッド、『ホイットニー・ヒューストン I WANNA DANCE WITH SOMEBODY』のケイシー・レモンズ、『ティル』のシノニエ・チュクウである。
配給会社別の実績を見ると、多様性への取り組みにおいてスタジオ間で明確な差が生じている。2022年は、ソニー・ピクチャーズ エンタテインメントが最も多くの女性監督(5作品)を起用した 。一方で、ライオンズゲート、パラマウント・ピクチャーズ、STXエンターテインメント、20世紀スタジオ、ウォルト・ディズニー・スタジオの5社は、女性監督を1人も起用していない。
また、女性監督のキャリアパスには「継続性」の欠如という構造的な問題が存在することが示唆された。16年間の調査期間中、女性監督の78.1%が興収上位作品を1本しか監督していない状態にあるのに対し、男性監督で同様の状態にあるのは54.8%となっている。白人男性監督が繰り返し機会を得やすい一方で、女性やマイノリティ監督には2作目以降のチャンスが巡ってきにくい状況にあると思われる。
業界内でたびたび挙がる「適任者がいない(パイプラインの問題)」という主張や「実力主義の結果である」という主張は、データによって否定されている。サンダンス映画祭(2015-2023年)のコンペティション部門における女性監督比率は41.8%、マイノリティ監督は41.8%に達している。また、テレビドラマシリーズ(2020-21年)でも女性監督は38%、マイノリティ監督は34.5%を占める。インディペンデント映画やテレビ界には多様な人材が存在するにもかかわらず、高予算の長編商業映画になると、途端にその数が減少するのだ。
また、批評家のレビューを集計したMetacriticスコアの分析では、監督の属性による作品の質の差は確認できないという。むしろ、有色人種の女性監督作品の平均スコア(62.2点)は、白人男性(54.8点)、マイノリティ男性(54.5点)、白人女性(55.7点)のいずれよりも高い数値を記録しているという結果だ。
本レポートは、解決策はシンプルかつ明快であると結んでいる。「女性や有色人種をトップ映画の監督として雇用すること」。決定権を持つスタジオ幹部が、認知バイアスを排除し、すでに実績のある多様な人材に2度目、3度目の機会を提供することだとレポートは結論している。